上京就職は、東京に住まいを移して入社することを指す言葉です。しかし、上京して東京で働くのは難しいのではないか、と考え、悩んでしまう方もいるでしょう。
本記事では、難しいと言われる理由・東京での就職事情・挑戦するメリットとデメリットについて解説します。
成功させるためのコツも紹介するので、上京就職を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
上京就職が難しいと言われる理由

東京で就職するのが難しいと言われる理由には、就職競争率の高さや移動時間、費用が挙げられます。上京後に生活が上手く活かず、もともと住んでいた場所に戻る人もいるのが特徴です。
しかし、東京に就職することで得られるメリットも多くあるため、依然として人気が高いといった側面もあります。
そのため、東京で就職するメリットとデメリットについて正しく理解してから、自身は上京に向いているかどうかを判断しなければいけません。
ここからは東京における就職事情について説明していくので、情報の把握にお役立てください。
東京都の就職事情

東京の実際の状況を知れば、自分がやっていけるかどうかイメージしやすくなるのが利点です。
ここでは東京都の就職事情を知る手がかりとなる、人口と求人倍率について説明します。
- 東京都の人口
- 東京都の有効求人倍率
①東京都の人口
東京都の人口は2023年6月時点で約1,400万人で、過去最大となっています。
さらに、地方から移住している人数も増加傾向にあり、就職の競争率は高くなっていると推測されるのがポイントです。
そのためあらかじめ就職の難易度が高いことを把握し、メリットを感じられるか検討した上で上京する必要があります。
また、就活を有利に進めるためには、これまで以上にしっかりと選考対策をしなければいけません。
②東京都の有効求人倍率
東京の有効求人倍率は、職業安定業務の統計データによると2023年6月時点で1.46です(参考:厚生労働省)。
有効求人倍率は、数値が大きいほど就職しやすいことがわかり、1以上であれば採用が活発に行われているといった指標になります。
ただ、学生の就職活動では人気企業に応募が集中しがちなため、入社難易度が高い会社も多くあるのが注意点です。
業種別に見てみると、事務事業者は0.46と1を大きく下回っています。反対に保安職業従事者は11.65と飛びぬけて大きいのが特徴です。
上京して就職することのメリット5つ

上京することで得られるメリットを確認すれば、将来的に有益な選択かどうかを吟味しやすくなります。メリットの具体例は、以下の5つです。
- 仕事の選択肢が豊富
- 様々なキャリアを築ける
- 交通の便が良い
- 給料が高い
- プライベートの充実性が高い
①仕事の選択肢が豊富
仕事の選択肢が豊富で、自由度が高いのが東京で仕事を探すメリットです。特に都心には様々な企業が集中しているので、自分に向いている仕事を見つけやすくなります。
もともと目指したい方向性が決まっている場合は、自分の望んだ職種で働ける会社も豊富に存在しているため、より自分の好みに合った会社を選びやすくなるのが利点です。
地元にない企業で働く機会を掴み、都心ならではの経験をしたい人にも適します。
②様々なキャリアを築ける
上京によって様々なキャリアを築きやすくなる、といったメリットもあります。
仕事の選択肢が豊富な分、住んでいた場所と比べて自由度の高いキャリアプランを描けるのがポイントです。
都心の会社は最先端の事業を手掛けている場合もあり、より貴重な経験を積みたい人にも適しています。
東京の会社の社風を事前に調べて、若手から活躍できる会社を選んで就活を進めれば、実力を磨ける業務や、やりがいのある仕事に取り組みやすくなるのも特徴です。
③交通の便が良い

地方に比べて交通の便が良く、車を持っていなくても移動しやすいといった利点もあります。
電車やバスの運転本数が多く、交通網の整備されているため、通勤で困ることが少ないのがポイントです。
駅やバス停から近い位置にある住居を見つけられれば、アクセスの利便性をさらに高められます。
また営業職など、外回りが求められる仕事であっても移動の負担が少ないといった利点もあるでしょう。
④給料が高い
東京は、地方に比べて給料設定が高いといった特色もあります。最低賃金が地方よりも高く設定されているので、同じ仕事内容でも高い賃金を得やすいのが特徴です。
年収の伸びが大きい傾向もあり、実力を磨いて勤続年数を重ねて昇格していけば、収入を増やせます。
社員寮や家賃補助、子育て援助などの制度を利用できる会社に就職できれば、生活費を節約しながら貯蓄額を増やしやすくなるのもポイントです。
⑤プライベートの充実性が高い
プライベートの時間が充実しやすいのも、都会ならではの強みです。
商業施設や飲食店が豊富に存在しているため、休日に好きな洋服を買いに行ったり、映画やライブを楽しんだりできます。
また、平日のランチタイムも充実した時間を過ごしやすいのが利点です。東京で憧れの場所がある場合は、自由時間に通って楽しい時間を満喫できます。
休日にリフレッシュできれば仕事のモチベーションにつなげられるのもポイントです。
上京して就職することのデメリット3つ

上京して会社に勤めることでのデメリットもチェックすれば、リスクを考慮した上で自分に合った選択をしやすくなります。注意しておくべき点は、以下の3つです。
- 物価が高い
- 通勤時間が苦しい
- 地元への帰省時間が少なくなる
①物価が高い
東京は地方に比べて給料が高いですが、その分物価が高いため注意が必要です。地方の生活と同じ感覚でお金を使っていると、家賃の支払いが難しくなるリスクもあります。
なるべく自炊を心がけるなど、節約できる点に気を配り、ガス代や水道代などの支払いが滞らないように注意しなければいけません。
給料の金額によっては、服装や娯楽に対して思ったよりも自由にお金を使えないこともあります。
後先を考えずに過ごしていると生活が苦しくなる可能性を考慮することも大切です。
②通勤時間が苦しい
働く人口が多いため、通勤時間に満員電車に見舞われることが多々あります。
人の波に飲まれて降りるべき場所で降りられなかったり、人混みの中で苦しい思いをしたりしながら会社に行かなくてはいけないのがリスクです。
通勤手段が豊富ではありますが、一定の時間に利用客が集中しやすいため、早起きして電車に乗る時間を早める、バスで通える会社や家を選ぶといった対策を取らなければいけません。
疲れて帰る時に椅子に座れないなどの状況でストレスを溜めないメンタルの強さが必要です。
③地元への帰省時間が少なくなる

地元への帰省時間が少なくなるのも、人によってはデメリットになりえます。
東京と地元に距離がある場合は、以前住んでいた場所に帰る時間が減るため、仲が良い友達と会って息抜きがしづらくなるのが懸念点です。
またホームシックになるリスクも考えられます。
上京先で知り合いがおらず、会社でもカジュアルに話せる人がいない場合、自分で居心地よく過ごせる場所を見つけなければなりません。
上京就職を成功させる秘訣3つ

上京就職を成功させる秘訣を知っていれば、失敗しないよう対策を練りやすくなります。東京での就職が上手く行くかどうかの分岐点は、以下の3つです。
- 東京で就職したい理由を明確にする
- 貯金をしておく
- 情報収集をこまめに行う
①東京で就職したい理由を明確にする
東京で就職したい理由をはっきりと伝えられるように準備しておくことが大切です。面接ではなぜ地元での就職は考えなかったのか、聞かれる機会が多くあります。
そこで明確な回答ができないと、計画性がない印象になってしまうため、対策が必要です。自分の将来を考えた上で決断したことが伝わる回答であれば、好印象を与えやすくなります。
企業が自身を採用するメリットだけでなく、キャリアプランを練っていることを伝えるようにしましょう。
②貯金をしておく
事前に貯金をしっかりとしておき、生活資金として利用できるお金に余裕を持たせるようにしましょう。
上京後は、就職するにも生活するにも何かとお金がかかります。元々の貯金額が心もとないと、仕事が安定するまで生活が苦しい状態に陥りやすいです。
貯蓄が尽きてしまって実家に帰る、などのケースにはならないよう、生活費は想定よりも多めに見積もっておき、お金の使い方のシミュレーションをしておきましょう。
③情報収集をこまめに行う
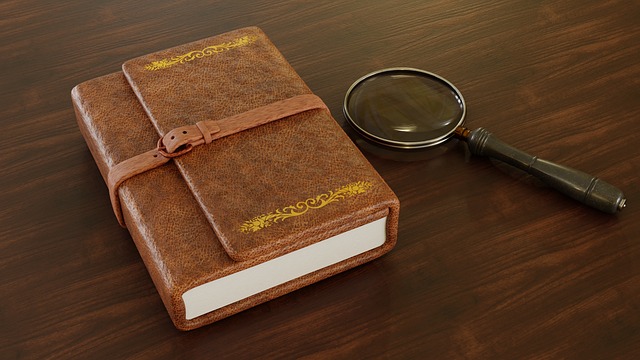
賢く立ち回るためには、情報収集をこまめに行うことも大切です。
都心では仕事の幅が広いですが、その分情報量も多くなるため、自分が勤めたい会社の情報をしっかりと調査し、分析しておく必要があります。
自己分析と企業研究を丁寧に行っていれば、面接で踏み込んだ質問をされても対応しやすくなるのがメリットです。
また、会社の立地や福利厚生などを確認して、生活費を抑える方法をリストアップしておくのも手となります。
成功する秘訣を踏まえて上京就職をしよう!
成功する秘訣を踏まえて、上京就職を目指しましょう。
東京は人口が多いため、施設や移動手段が充実しているメリットがありますが、生活費が高いなどのデメリットがあります。
自分の中で利点と欠点を天秤にかけ、自分にとって望ましい選択を取るようにしましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









