公務員試験を調べてみると、上級・中級・初級などに分類されていて、どれを選べばよいのか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、大卒程度の試験内容である上級公務員について解説します。公務員を目指している人は、ぜひ試験対策の参考にしてみてください。
就活全般をサポート!便利なツール集
- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ
- LINE登録でESを自動作成してくれる
- 2志望動機テンプレシート|時間短縮
- 早く質の高い志望動機が作れる!
- 3自己PR自動作成|お手軽完成
- 基本構成を押さえてすぐに作成!
地方公務員の仕事内容を簡単に説明

地方公務員は、県庁や市役所などの公的な施設に勤務します。ここでは、次の3つに分類して地方公務員の仕事内容をまとめました。
- 基礎自治体での仕事
- 広域自治体での仕事
- 一般職と特別職
地方公務員の特徴は、自治体ごとに採用される点です。各仕事の内容を把握し、自分の理想的な働き方を考える際の参考にしてください。
①基礎自治体での仕事
基礎自治体とは、特別区・市町村を指します。特別区職員・市町村職員として、行政の窓口業務等を行うのが主な仕事内容です。
また、行政枠で採用された場合は、以下のような業務も担います。
- 保育園の入所
- 小中学校等の運営
- 道路や都市計画
- 保険
- 水道事業
- ごみの収集・処理
特別区・市町村内での勤務になるため、転勤はありません。一方で、公務員はジョブローテーションを採用しているため、部署異動が頻繁です。
②広域自治体での仕事
広域自治体とは、政令指定都市・都道府県を指します。基礎自治体の職員と比べ、より広い範囲での行政サービスが業務の対象です。
政令市職員・都道府県庁職員として採用された場合、以下のような業務を行います。
- 市町村に関する連絡調整
- 農地や都市計画
- 道路・河川・海岸等の建設・整備
- 高等学校等の運営
- 農林水産業・商工業等の産業振興
採用された都道府県内、または政令指定都市が異動範囲となるため、転居を伴う可能性がある点は考慮してください。
③一般職と特別職
公務員は、一般職と特別職に分類されます。一般職は事務・行政系です。行政窓口のほか、学校事務・警察事務も該当しています。
特別職は、心理職・福祉職・技術職・公安系です。専門的な知識が求められるため、資格や実務経験が試験の受験資格に課せられています。
公安系は、警察官・消防官が該当。筆記試験・面接に加え、身体検査や体力検査があるため、健康的な肉体のための運動が欠かせません。
地方上級公務員と中級・初級の違い

実は、「上級公務員」という肩書きはありません。この「上級」とは試験用語で、試験レベルの目安です。
地方上級は大卒程度、地方中級は短大卒程度、地方初級は高卒程度の学力とされています。あくまでも目安のため、受験に際して学歴は必須ではありません。
試験名称は自治体によって異なり、大卒程度の公務員試験は、上級職・1類・1種・大卒程度などと呼ばれています。
初任給は中級合格者・初級合格者とあまり差がありませんが、上級合格者は昇進スピードがはやいため、長い目で見たときに年収が高くなりますよ。
地方上級公務員が昇進に有利な2つの理由

地方上級公務員が昇進に有利な理由として、次の2つの理由をチェックしておきましょう。
- 昇進のスピードがはやくなる
- 自治体をまたいでの異動はない
理由を知ることで、キャリアパスがイメージしやすくなりますよ。
①昇進のスピードがはやくなる
大卒程度の学力が求められる地方上級試験は、国家公務員の一般試験と同程度の難易度です。そのため、国家公務員一般試験の合格者程度の能力があると判断されます。
地方上級公務員は組織の幹部候補です。勤務年数が経つほど責任があるポストに配属されるようになるため、中級・初級と比較すると昇進のスピードがはやくなります。
加えて、公務員は勤務年数と与えられた責任度によって給与が高くなるため、幹部候補である地方上級公務員は年収が高い点も特徴です。
②自治体をまたいでの異動はない
採用された都道府県が異動範囲のため、一つの自治体に関する専門性を磨き上げられます。また、市町村職員よりも広域が対象なので、より広い視野で自治体を把握できるでしょう。
自治体をまたいだ異動がないため、蓄積された自治体の行政に関する知識や経験が役立つのも、地方公務員ならではです。
都道府県の行政を広域で担うため、地方自治体の専門家とも言えます。また、部署異動が頻繁なため、短期間で業務を覚えて即実行に移せる柔軟性と対応力が不可欠です。
地方上級公務員試験の内容、難易度

地方上級公務員試験は、全国型・関東型・中部北陸型などに分かれています。地方自治体に共通している試験の流れは、次の内容です。
- 【1次試験】2つに分かれている教養科目
- 【1次試験】4つに分かれている専門科目
- 【2次試験】面接
1次試験は、2つに分類できる教養科目と4つに分類できる専門科目があります。ここでは、各試験の内容や難易度を解説しているので、受験の目安にしてください。
【1次試験】2つに分かれている専門科目
1次試験は筆記です。教養科目は、一般知識分野と一般知能分野に分けられます。
一般知識分野は、社会科学・人文科学・自然科学です。
| 社会科学 | 政治、経済、法律、時事(社会) |
| 人文科学 | 日本史、世界史、地理、文学・芸術、思想 |
| 自然科学 | 数学、物理、化学、生物、地学 |
一般知能分野は、数的処理と文章理解です。
| 数的処理 | 判断推理、数的推理、資料解釈 |
| 文章理解 | 現代文、英文、古文 |
ほとんどの自治体では全問解答が必須の択一式のため、上記5科目の学習を計画的に進めましょう。
【1次試験】4つに分かれている専門科目
教養科目よりも専門性が高いのが、専門科目です。専門科目は、法律系・経済系・行政系・商業系に分けられます。
| 法律系 | 憲法、行政法、民法、労働法、刑法 |
| 経済系 | ミクロ経済学、マクロ経済学、財政学 |
| 行政系 | 政治学、行政学、社会政策、国際関係 |
| 商業系 | 経営学 |
全国型は全問解答必須で、関東型・中部北陸型は選択式です。各自治体の形式を確認しましょう。
また、心理職や福祉職など専門性が高い分野を受験する場合は、上記のほかに心理・福祉などの学習も不可欠です。
【2次試験】面接
個人面接・集団面接のいずれかが必ず実施されます。自治体によって面接の形式は異なるため、事前の情報収集と対策は欠かせません。
また、適性試験や論作文も2次試験で行います。適性試験は1次試験で行う自治体もあるので、あらかじめ確認してください。
論作文では、制限時間内に指定された文字数を守って書き上げる必要があります。また、面接では志望動機を考えるだけではなく、慣れない言い回しを練習しておきましょう。
地方上級公務員合格への道
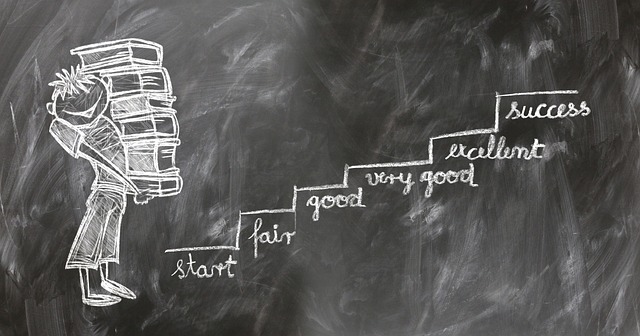
地方上級公務員試験に合格するためには、計画的な学習が不可欠です。ここでは、以下の2点に注目しています。
- 平均1000時間の勉強量を確保しよう
- 予備校に通う選択肢もある
学習計画を立てる際には、この項目も参考にしてみてください。
①平均1000時間の勉強量を確保しよう
公務員試験の範囲は、教養科目・専門科目をあわせると30科目にもおよびます。有している知識にもよりますが、上級職の公務員試験に合格するには1000時間の勉強時間を確保しましょう。
学校生活やアルバイトなどの日常生活と両立するためには、学習する科目に優先順位をつけ、計画的に学習を進めることが大切です。
30科目は、インプットが中心の暗記科目と、内容の理解が不可欠な専門科目に分けられます。とくに、法律・経済系は知識が無いと理解しにくい場合があるので、優先的に学習しましょう。
②予備校に通う選択肢もある
公務員試験は独学でも対策はできますが、人によってはペース配分が苦手だったり、面接が苦手だったりしますよね。
公務員試験の学習方法は、独学の他に、
- 予備校に通う
- 大学が実施している公務員試験の対策講座に参加する
などがあります。
試験内容の範囲が広い地方上級公務員試験は、受験の1~2年前には勉強を始めるのがベターのため、大学3年生から対策勉強を開始する人は予備校や対策講座がおすすめです。
1人で黙々と学習を進めても良いですが、より効率的な勉強方法を求める人は、これらの講座を活用しましょう。
試験対策をすれば地方上級公務員になれる!

地方上級公務員になるためには、試験対策が欠かせません。本記事を参考に学習計画を立て、上級公務員試験に合格しましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









