グループディスカッションの面白いテーマ12|上手く進めるコツも
グループディスカッションのテーマには、個性的なものもいくつかあります。しかし、どんなテーマの対策をしておけばよいのかわからず、悩んでしまう人もいるでしょう。
本記事では、グループディスカッションの種類・テーマの意図・テーマの具体例について解説します。上手に進めるためのコツも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
全て無料!面接対策お助けツール
- 1実際の面接で使われた面接質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作成できる
- 3強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。
グループディスカッションの種類4つ

グループディスカッションの種類を知っていれば、それぞれの特徴を把握しやすくなります。テーマは、以下の4種類に分類可能です。
- 課題解決型
- 選択肢型
- 討論型
- 自由アイデア型
①課題解決型
課題解決型は、提示されている課題に対して解決策を考えることが求められます。課題に対する認識のすり合わせが大切になり、改善するべきポイントの分析力も重要になるのが特徴です。
業界や仕事内容に関連した問題が出題されるケースでは、事業や会社への理解を深めておく必要があります。
テーマの種類の中ではよく出題されやすい傾向があるため、対策をしっかりと行っておくとさまざまなテーマに対応しやすくなるのが利点です。
②選択肢型
選択肢型は、テーマの中で複数の選択肢が与えられ、どれを選ぶべきかを考えるのが特徴です。
2択から選ぶケースも多く、選択肢を見比べてどちらを優先するべきなのか答えを出すことが求められます。
選択肢から想定されるメリットやデメリットを考えて、より説得力のある理由がある選択肢をチョイスしなければいけません。
意見が分かれた場合には、時間内にグループで意見をまとめて理由をつめていく必要もあります。
③討論型
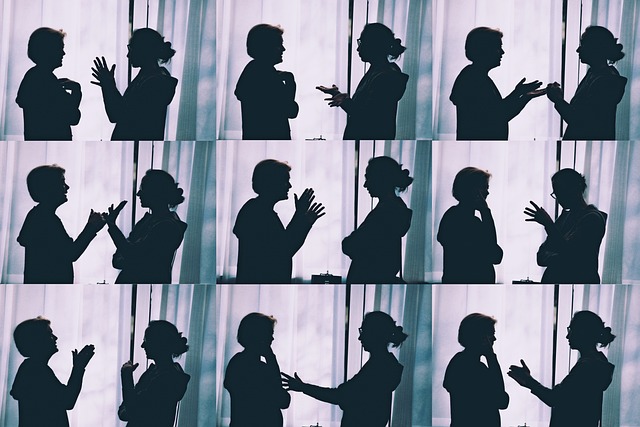
討論型は、与えられた課題に対して意見を交わしながら、結論を決めることが求められるテーマです。
正反対の選択肢が用意される場合には、意見が分裂しても冷静にそれぞれの正当性を評価して結論をまとめる力が必要になります。
また、テーマに対して何が適しているかを討論し、より適した解答を生み出すことが求められるパターンもあるのが特徴です。
自身の意見を通すことに注力しすぎず、あくまでも協力しながら最適な結論を導くことが重要になります。
④自由アイデア型
自由アイデア型は、テーマに対してどんなことが適しているのか、アイデアを出し合って決めることが求められます。
わかりやすい答えがない問いに対して考えさせるパターンが多く、さまざまな視点から問題を分析し、考えるスキルが必要になるのがポイントです。
積極的にアイデアを出していけるか、アイデアを方向性ごとにまとめて議論を進められるかどうかが見られます。
新しい発想で課題にアプローチするスキルを重要視している会社で出題されやすいです。
グループディスカッションで面白いテーマを用いる理由2つ

面白いテーマで議論をさせる理由を知っていれば、出題者の意図に合った姿勢で参加しやすくなるのがメリットです。
個性的なテーマを用意する意図としては、以下の2つが挙げられます。
- 緊張緩和のため
- 自由な発想を見たいため
①緊張緩和のため
緊張を緩和させて意見を活発に交わせるようにするため、個性的なテーマを用意している場合があります。
緊張してしまって議論が進みづらくならないように、と企業側が配慮して、より自然体で参加できるテーマが設けられることもあるのが特徴です。
また緊張によって本来の実力が出せない場合、参加者のポテンシャルを図りづらくなるといったデメリットもあります。
正当な評価ができるように面白いテーマを設けていることもあるのがポイントです。
②自由な発想を見たいため
自由な発想を見るために、あえて回答の幅が広い設問を出題するケースもあります。
よくあるテーマではある程度適切な答えが決まっているため、グループごとの回答に偏りが出る傾向があるのがデメリットです。
回答の自由度が高いテーマには、さまざまな視点から意見を生み出す力があるかどうか見たい、といった意図があると推測できます。
また、自由な意見が飛び交うテーマは1つの回答にまとめることが難しいため、状況から判断して適切な行動を取る力を持っているかどうかを確認できるのも特徴です。
グループディスカッションの面白いテーマ例

テーマの具体例をチェックすれば、どのようなテーマに臨む必要があるのかイメージしやすくなるのが利点です。ここでは、4種類のテーマの具体例を紹介します。
- 課題解決型の例
- 選択肢型の例
- 討論型の例
- 自由アイデア型
①課題解決型の例
課題解決型の具体例としては、以下の3つが挙げられます。
- 自社の農産物を一つ1万円で売る方法
- 夏を知らない人に説明する方法
- 施設の認知度を上げる方法
会社の業務に絡めた議題を用意するパターンでは、あらかじめ業界のトレンドや仕事内容を理解した上で、問題を分析する力が必要になるのが特徴です。
また、特定の条件下で相手にわかりやすく情報を伝える方法を考えさせるタイプのテーマもあります。
②選択肢型の例
選択肢型の具体例は、以下の3つです。
- 無人島に持っていくもの
- 理科と社会どちらが重要か
- 生まれ変わるなら「女」か「男」か
選択肢型のテーマでは、説明文である程度条件が絞られている中で、解答を選ぶことが求められます。
相反する選択肢からどちらかを選ぶ場合は、チョイスしなかった選択肢と比べて、説得力のある理由を説明できるかどうかが重要になるのがポイントです。
選択肢が決まっている分、話し合う時間を多くとれるため、より隙のない理由を考える必要があります。
③討論型の例

討論型のテーマの具体例には、以下の3つが挙げられます。
- 小学生から受験をさせるべきか
- 時間が戻せるなら未来・過去どちらにいくべきか
- 魔法が使えたらどのようなものがあれば社会に役立つか
人によって意見が分かれやすいテーマが多いため、あらかじめ意見が対立した時にどう対処するべきか考えておくと対応しやすいです。
それぞれの意見の強みや弱みを考えてまとめたり、意見の良い部分を抽出して組み合わせ、より適した解答を作ったりする必要があります。
④自由アイデア型
自由アイデア型では、以下のように決まった選択肢がないテーマが出題されます。
- 全国の小学生の学力を高める方法
- 幸せを定義するなら?
- 新しいインバウンド事業のサービス
抽象的な話題についてスムーズに話し合うためには、まず掲げられているテーマに対する認識のすり合わせを行って、ある程度方向性を決めておくと答えがまとまりやすいです。
事業に絡めた内容の場合は、新しい発想も取り入れつつ、既存事業についての情報も頭に入れて考える必要があります。
グループディスカッションを進めるポイント3つ

グループディスカッションをスムーズに進める方法を知っていれば、緊張したとしても冷静に対処しやすくなります。議論を上手に進めるコツは、以下の3つです。
- 流れを把握する
- 役割分担をする
- 話しやすい雰囲気を作る
①流れを把握する
議論を進める流れを知っていれば、進め方を頭の中で描きながら取り組みやすくなります。基本的な流れは、以下の通りです。
- 前提の把握
- 現状の課題の整理
- アイデア出し
- 結論まとめ
- 資料作成
- 発表準備
まずテーマについて全員の認識の方向性をまとめてから、課題について分析し、アイデアを出す必要があります。
結論をまとめて終わりではなく、資料を作って発表準備をする時間も設けなければいけないため、時間配分を決めておきましょう。
②役割分担をする
役割分担をしておくことで、議論を円滑に進めやすくなるのもポイントです。議論には、司会者・タイムキーパー・書記・発表者などの役割があります。
自分が得意な役割を把握しておくと、自身の強みを活かしながらグループに貢献しやすくなるのがメリットです。
タイムキーパーは議論の軸からずれている時に修正するよう伝える、監視者の役割を務める場合もあります。
司会者は議論の流れを読みながら冷静な提案を行う役割も求められるのが特徴です。
③話しやすい雰囲気を作る

話しやすい雰囲気を作ることを心がければ、緊張をほぐして議論が活発になるよう働きかけられます。
最初のアイスブレイクでタメ口を用いるなどの手段を取り入れることで、メンバー間の距離を縮めることが可能です。
ただ自己紹介を簡単に済ませるのではなく、親しみやすい情報を付け加えると親近感を持たせて意見を言い出しやすい雰囲気作りができます。
議論が熱くなっても強い言葉を使いすぎないように心がけることも重要です。
面白いテーマは楽しんでディスカッションしよう
面白いテーマは楽しみながら、活発に議論を進めましょう。個性的なテーマは緊張をほぐしたり、自由な発想力を見たりするために出題されるのが特徴です。
議論を進める流れや役割分担についても理解しておき、限られた時間内で説得力のある結論を発表できるようにベストを尽くしましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









