漢検を取得している人は多く、履歴書に書いて就活のアピールに活用しようと考えている人も多いですよね。ですが、いざ履歴書に書こうとしても「どうやって書けばいいの?」と悩んでしまうでしょう。
そこで、本記事では履歴書に記載できる漢検の級や具体的な書き方、よくある疑問点までくわしく解説します。ぜひ、これからの就活の参考にしてみてくださいね。
履歴書はこれで完璧!お助けツール集
- 1AIで自動作成|作成を丸投げ
- スマホで記入項目をすぐに作成できる
- 2志望動機テンプレシート|簡単作成
- 受かる志望動機が5STEPで完成!
- 3自己PR作成ツール|受かる自己PRに
- 3分で好印象な自己PRが作成できる
履歴書に記載できる漢検の級を解説

履歴書に記載して効果的なアピールとなる漢検の級は、2級以上とされています。
漢検は10級から1級まであり、どの級でも履歴書に記載が可能です。ただし、2級以下の漢検を書いても、選考に有利にならない可能性があります。
漢検2級は、常用漢字を全て読み書きできるというレベルです。このため、2級以下を履歴書に書いてもあまりアピールにはつながらないでしょう。
履歴書に書けないわけではありませんが、就活で評価基準となるのは2級からであると念頭に置いてください。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、ES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
漢検を履歴書に書くメリット3つ

履歴書に漢検を書くことで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、漢検を履歴書に書くことで得られる3つのメリットを紹介します。
メリットを知っておけば面接などでも活用できるので、ぜひ覚えておいてください。
- 2級以上は採用に有利に働く
- 言語力の高さをアピールできる
- 一般常識をアピールできる
①2級以上は採用に有利に働く
漢検2級以上は、履歴書に書くことで採用試験に有利に働く可能性があります。漢
検2級は常用漢字の読み書きができるという判断基準になるので、仕事をする上で資料の読み書きがスムーズにできると印象付けらるのです。
また、資格を持っているということは、目標に向かって努力できるという、プラスのイメージを与えられます。資格は内容も大切ですが、その資格を取得するまでの過程も評価されるのです。
漢検2級以上を持っている人は、ぜひ履歴書に書いてアピールにつなげてください。
②言語力の高さをアピールできる
漢検を持っていれば、一定の語彙力や漢字力があると採用担当者に印象付けられます。
仕事をする上で漢字は毎日のように触れるものです。漢検を持っていれば、漢字を正しく読んで理解できるとアピールできるのです。
また、語彙力が豊富であれば相手に伝える能力も自然と高くなり、プレゼンや商品説明、取引先との話し合いなどで有利に働きます。
漢検を持っていると履歴書に書けば、仕事をしていく中でどんな活躍ができるか、採用担当者にイメージしてもらいやすいでしょう。
③一般常識をアピールできる
漢字の読み書きは、社会人として基礎中の基礎です。書類やメールなど、毎日のように漢字に触れ、内容を正しく理解する必要があります。
漢検を持っているということは基礎を正しく理解できるというアピールにつながり、一般常識を持っていると印象付けられるのです。
一般常識が不足していると、さまざまなトラブルにつながります。場合によっては、漢字を知らなかったせいで大きなトラブルの原因にもなりかねません。
漢検取得を履歴書に書いて、仕事をする上で必要な言葉や文字を理解できるとアピールしてください。
漢検の履歴書への書き方
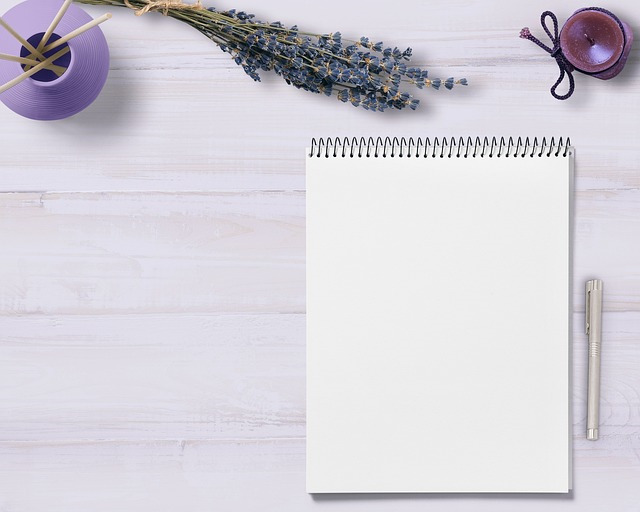
いざ漢検を履歴書に書こうとしても、どうやって書けばいいかわからないという人も多いのではないでしょうか。ここでは、正しい書き方を3つのポイントにまとめて紹介します。
書き方に迷っている人はぜひ参考にしてみてください。
- 正式名称で書く
- 取得年月を必ず書く
- 記入例
①正式名称で書く
履歴書に漢検を書くときは、「漢検」と書かないように気を付けましょう。「漢検」は略称で、履歴書に略称を書くのはNGとされています。
漢検の正式名称は「日本漢字能力検定」です。正式名称の後に何級を持っているかを書きましょう。例えば2級を持っていたら「日本漢字能力検定2級」と書きます。
略称で書いてしまうと、正式な資格として認められなかったり、履歴書の正しい書き方を知らない人だと思われてしまい、逆効果です。必ず正式名称で書くようにしてください。
②取得年月を必ず書く
漢検を履歴書に書く際は、必ず取得年月を書いてください。取得年月日を忘れてしまった場合は、漢検に合格した際に貰える「合格証書」で確認しましょう。
漢検に有効期限はありません。履歴書に書いて採用を有利に進めるのであれば、間違えがないように合格証書を参考にして、正しい情報を記載してください。
間違えた情報を書くと、採用されたとしても後々のトラブルにつながる可能性があるので、気を付けましょう。
③記入例
漢検は「令和〇年×月 日本漢字能力検定2級 合格(または合格)」と書くのが正しい書き方です。
履歴書内の西暦和暦は統一するようにしましょう。バラバラに書いてしまうと、採用担当者が履歴書を読みにくくなってしまいます。
また、「この人は書類をちゃんと書けない人なのでは?」と、悪い印象につながるかもしれません。
立派な資格を持っていても、履歴書のルールに沿って正しく内容を書けない人は、採用へのハードルが高くなってしまうのです。履歴書は正しく書くように、常に意識してくださいい。
漢検を履歴書に書く場合にすべきこと3つ

漢検はうまく活用すれば就活を有利に進められる材料になります。効果を最大限に活かすために、漢検を履歴書に書く場合は以下の3つを確認してください。
- 合格証書が手元にあるか確認する
- 余裕をもって漢検の試験を受ける
- 漢検CBTを活用する
①合格証書が手元にあるか確認する
漢検にすでに合格している場合、合格証書が手元にあるか確認してください。
履歴書に書く際、何級を持っているかだけでなく、合格した年月も書く必要があります。正しい内容を書くためには、合格証書に書かれている取得年月を確認しなければなりません。
また、場合によっては会社に合格証書の提出を求められるケースもあります。このため、履歴書に書く前に合格証書が手元にあるか確認しましょう。
合格証書がない場合は、日本漢字能力検定協会に再発行してもらうか、公式サイトから申し込んで取得情報を教えてもらう手続きをしてください。
②余裕をもって漢検の試験を受ける
漢検の試験を受けてから結果が出るまでは、一定の時間がかかります。就活で漢検取得をアピールしたいのであれば、余裕を持って漢検の試験を受けましょう。
漢検の試験は定期的におこなわれています。ただし、いつでも受けられるというわけではありませんし、一度で合格するとも限りません。
漢検の試験を受けるのであれば、就活のスケジュールに合わせて、きちんと予定を立てて挑みましょう
③漢検CBTを活用する
漢検の資格をすぐに取得したいのであれば、いつでも試験が受けられる漢検CBTを活用しましょう。
漢検CBTとは、パソコンを使った試験のことです。専門の会場で行われる試験ですが、場所によっては日曜や祝日でも試験が受けられます。
また、漢検CBTは約10日で合否結果が出るので、通常であれば40日程度かかる試験と比べてすぐに結果を知ることができます。
ただし、漢検CBTは10級から2級までしか受けられないので、それ以上の級を目指している人は、年3回開催の漢検試験を受けましょう。
履歴書に漢検を書く際によくある質問集

漢検を勉強中の人や合格証書をなくした場合など、履歴書に書くときに迷ってしまうケースもあるでしょう。ここでは、よくある疑問点をまとめて紹介しています。
当てはまる方は参考にしてみてください。
- 勉強中や結果待ちの場合
- 合格証書を無くした場合
①勉強中や結果待ちの場合
漢検の資格は持っていないけれど勉強している場合は、勉強している級と併せて「合格に向けて勉強中」と書いても構いません。
資格は内容だけでなく取得に至るまでの過程も評価されるので、勉強中であることをアピールして採用につなげましょう。
また、試験を受けたけれどまだ手元に結果が来ていない場合は、履歴書に「合格予定」と書いてください。
ただし、履歴書に嘘を書くのはNGです。本当は勉強していないのに「勉強中」と書いてしまうと、後々のトラブルにつながります。
②合格証書を無くした場合
漢検に受かると合格証書がもらえますが、これをなくしてしまう人は珍しくありません。もし合格証書をなくしてしまった場合、日本漢字能力検定協会のWebサイトから受験履歴を確認できます。
Webサイトにある「受験履歴照会依頼書」をダウンロードして必要事項を記入して、本人確認書類のコピーと一緒に協会へ送付しましょう。この手続きをすれば、協会から合格者情報を教えてもらえます。
合格証書を再発行してもらいたい場合は、協会に再発行申請書を送る必要があります。
漢検を履歴書に書いて就活を有利に進めよう!

漢検は履歴書に書いて上手く活用すれば、採用試験を有利に進められます。漢字は仕事をする上で毎日触れるものなので、資格を持っていない人も今後のために試験を受けてみてはいかがでしょうか。
漢検の勉強で得た知識は、就活を有利に進めるだけでなく、社会人としてのこれからの生活にきっと役立つでしょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









