出版社は、雑誌や書籍などの制作に携われる会社です。
集英社や講談社など、知名度が高い会社が多いですが、具体的にどんな仕事に携わるのか、就職対策はどうすればよいのかわからず、困ってしまう方もいるでしょう。
本記事では、出版社の概要や現状と今後・仕事内容・やりがい・有名企業の例・就職のためにやるべきことなどについて解説します。
学歴フィルターの有無なども含めて知りたい方は、ぜひご覧ください。
出版社の概要
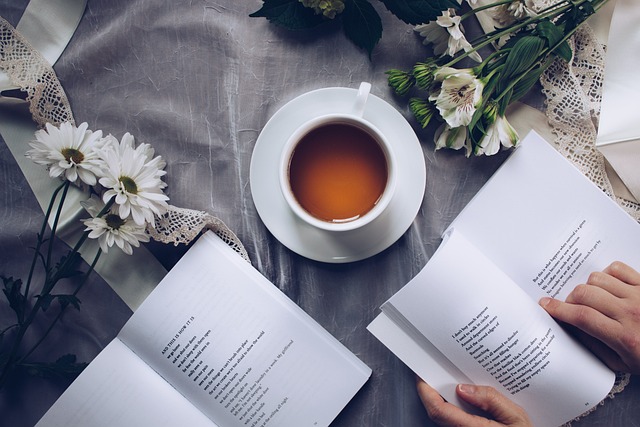
出版社とは、本や雑誌などの企画や制作に携わり、形にしていく業務を行う会社です。
いろいろな分野の作品を手掛ける総合出版社・参考書などを専門に制作する専門出版社・小説を主に制作する文芸書出版社などに分類できます。
就活生から高い人気を誇る会社が多く、制作した作品の宣伝業務も行うのが特徴です。
また、子どもから大人まで読んでいる少年漫画の編集や、トレンドを発信していくファッション雑誌の企画などに携われるといった魅力があります。
印刷会社に向けて発注を行うなど、さまざまな会社と関わりながら業務を進めていくのもポイントです。
出版社の現状と今後

出版社の現状と今後について知っていれば、会社が抱えている課題や将来に向けてのプランへの理解を深められるのが利点です。
ここでは現状と今後の2つに分けて説明します。
- 出版社の現状
- 出版社の今後の課題
①出版社の現状
出版社の現状として、売り上げは紙媒体と電子媒体ともに増加傾向にあることが挙げられます。
電子媒体が特に好調で、スマホやタブレットで雑誌や漫画、小説を読む方が増えていることが主な理由です。
電子媒体では特に漫画の売り上げが大きく増加していて、家で手軽に楽しめる漫画の需要が高まっています。
一方で紙媒体の発行部数は紙の本は場所を取ること、書店に買いに行かないと読めないことが理由となり、年々減少しているのが特徴です。
②出版社の今後の課題
出版社の今後の課題として、電子媒体を中心に据えた新しいメディア展開を行わなければいけないことが挙げられます。
今後紙媒体の作品はさらに売り上げが減少する見込みとなっているのが特徴です。
電子媒体のコンテンツの充実性を高めたり、書籍をコンセプトにしたホテルやカフェなど、新しいビジネスを展開したりする姿勢が重要となります。
また、書籍の映像化やアニメ化を手掛けるメディア事業に乗り出すなど、新たな試みに挑戦する会社も増加しているのがポイントです。
【職種別】出版社の仕事内容6つ
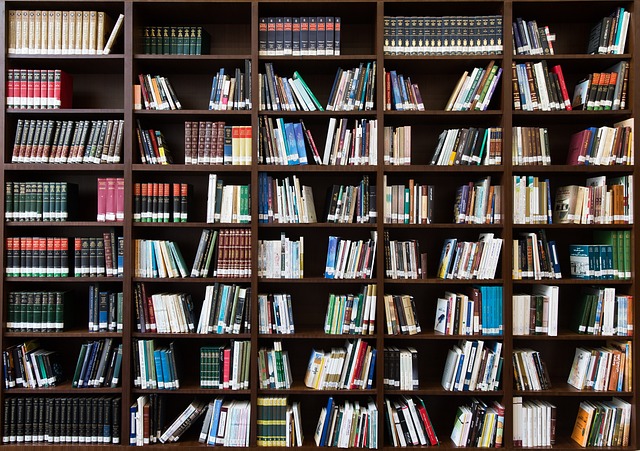
出版社の仕事内容を確認すれば、どんな業務に携わる機会があるのかイメージしやすくなります。具体的な内容は、以下の6つです。
- 編集
- 営業
- 制作や校閲
- デジタル推進
- 版権
- 管理
①編集
編集では、雑誌に使われる記事の提案を行う仕事や、取材や撮影の方向性を決める仕事・文章校正などの業務に携わります。
漫画や雑誌など、関わる作品によって仕事内容が変わっていくのが特徴です。
締め切りに間に合うよう全体の進捗を確認したり、作家のスケジュール調整を掛け合ったりする必要もあります。
さまざまな作業を同時に進行していけるスキルや、多様な立場の人と関われるスキルが重要になる仕事です。
②営業
営業は、広告を出したい企業に向けて、広告スタイルの提案や費用の交渉を行う広告営業と、書店などに対して発注数を増やしてもらえるよう働きかける書店営業の2種類に分かれます。
広告営業は出版社の利益を向上させるために大切な役割を果たしているのが特徴です。
また、書店営業では書店に働きかける業務を担当している出版取次会社に向けても営業を行います。
販売量を増やすために、著者による直筆のサイン会や作品についてや著作活動について聞けるトークショーを開催することもあるのがポイントです。
③制作や校閲
制作では雑誌に使う企画の打ち合わせやデザインを行い、校閲では事実と異なる文章や誤った表現、一貫性の有無などを確認し修正を行います。
会社によっては、編集の仕事に制作や校閲が含まれることもあるのが特徴です。
制作業務では外部の企業に発注を行うこともあり、正しさとスピード感を重視した連絡を心がけなければいけません。
また、校閲は作品の信頼性を高めるために大切な役割を担っていて、誤字脱字だけでなく事実の確認を行い、正しい表現に変更する業務も担当します。
④デジタル推進

デジタル推進では、作品のデジタル化作業を担当したり、デジタル化による収益向上を図ったり、紙媒体と電子媒体で差別化をしたりするのが特徴です。
会社によっては営業部や制作部の業務に含まれるほか、DX推進部として部門が設けられていることもあります。
特に近年は電子媒体のニーズが高まっていることから、利益を拡大していく上で重要度が高い仕事になっているのがポイントです。
デジタル技術を活用して制作物にどんなメリットをもたらせるか考えるスキルも必要になります。
⑤版権
版権では、書籍を制作するにあたって著作者が出版社に与える権利に関わる業務を行います。
出版社は版権を与えられた場合、受け取った原稿を6か月以内に出版したり、ネットを通じて作品の発表を行ったりすることが法律で定められているのが特徴です(参考:著作権法)。
版権に関する仕事をするには、著作権についての専門的な知識が必要になります。責任感を強く持てる人が適しているのもポイントです。
⑥管理
管理では、会社に必要な人材を選ぶ仕事・会社の会計処理に携わる仕事・総合事務としての仕事などを担当します。
マスコミに対する処理を担当する広報業務を行う場合もあるのがポイントです。
人材関係の仕事では、新卒採用や経験者採用に関する業務を行い、会社にふさわしい人材を見つけるために選考を実施します。
インターンシップや説明会などの企画や実施にも携わるのが特徴です。社員の給料管理や昇給額のチェックなども行います。
出版社の仕事のやりがいや魅力
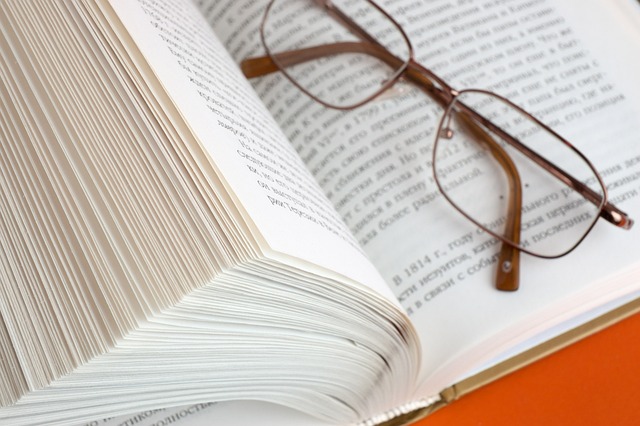
出版社の仕事には、自分が企画したものが世の中に出て、多くの方に読んでもらう喜びを感じられる、といったやりがいがあります。
会社によっては、自身が子どもの頃から慣れ親しんでいた漫画や雑誌の仕事に関われるのが大きな魅力です。
ファッション雑誌の制作に携わる仕事では、トレンドの最前線に立って華やかな紙面をデザインし、人々の生活に彩りを加えられます。
また、媒体を問わず、世の中に新しい作品を生み出すやりがいが感じられる仕事でもあります。
1つ1つの業務は地道なものであっても、作品を読んだ方の感想や反響を得られる分、大きな達成感を得られるのが強みです。
【業界最大手】出版社の有名企業5つ

出版社の有名企業について情報をチェックすれば、業界の代表的な会社が発行している雑誌や売り上げの違いなどを比較できます。
大手企業は、以下の5つです。
- 集英社
- 講談社
- 小学館
- KADOKAWA
- 文藝春秋
①集英社
| 社名 | 株式会社集英社 |
| 創業日 | 1926年8月8日 |
| 売り上げ | 2,096億8,400万円 |
| 従業員数 | 764名(男性418名 女性346名) |
| 代表的な雑誌や書籍 | ・週刊少年ジャンプ ・りぼん ・non-no ・Myojoなど |
集英社は週刊少年ジャンプなどの有名作品を制作するほか、読書推進活動やバスケットボール選手を目指す高校2年生を対象としたスラムダンク奨学金などの活動も展開している会社です。
1day仕事体験などのイベントも開催されています。
②講談社
| 社名 | 株式会社講談社 |
| 創業日 | 1909年11月 |
| 売り上げ | 1,708億円 |
| 従業員数 | 945人 |
| 代表的な雑誌や書籍 | ・週刊少年マガジン ・週刊現代 ・FRIDAY ・ViViなど |
講談社は光文社やキングレコード、一迅社などを関連会社に挙げる、長い歴史を持つ会社です。
鹿島建設とコラボしたセミナーや、オンラインでの合同説明会などを実施しています。大学に向けて企業セミナーを開催しているのも特徴です。
③小学館

| 社名 | 株式会社小学館 |
| 創業日 | 1922年8月8日 |
| 売り上げ | 1,084億7,100万円 |
| 従業員数 | 696名 |
| 代表的な雑誌や書籍 | ・週刊少年サンデー ・ちゃお ・女性セブン ・CanCamなど |
小学館はコミック雑誌やファッション雑誌のほか、小学生向けの図鑑NEOが20周年を迎えるなど、子供の教育向け作品も長く取り扱っている会社です。
マイナビやキャリタス就活によるセミナーや、さまざまな大学で業界研究セミナーを開催しています。
④KADOKAWA
| 社名 | 株式会社KADOKAWA |
| 創業日 | 1945年11月10日 |
| 売り上げ | 2,554億円 |
| 従業員数 | 5,349人 |
| 代表的な雑誌や書籍 | ・角川文庫 ・電撃文庫 ・レタスクラブ ・週刊ファミ通など |
KADOKAWAは出版業だけでなく、書籍の映像化やアニメ化を行う映像業・ゲーム制作・Webサービス運営業など、さまざまな事業を展開している会社です。
総合職のみを募集していますが、17種類の職種から希望するものによって選考内容が変わっていく、といった特徴があります。
⑤文藝春秋
| 社名 | 株式会社文藝春秋 |
| 創業日 | 1923年1月 |
| 売り上げ | 194億円 |
| 従業員数 | 351名 |
| 代表的な雑誌や書籍 | ・文藝春秋 ・オール讀物 ・週刊文春 ・CREAなど |
文藝春秋は菊池寛が創業し、創刊号には芥川龍之介や川端康成が参加したことで知られる会社です。
雑誌のほか政治や歴史をテーマとした硬派な文春新書なども制作していて、雑誌広告業や自費出版業も行っています。
雑誌編集部・書籍編集部・デジタル部・ビジネス関係部で募集をしているのが特徴です。
出版社に向いている人の特徴4つ

出版社に向いている人の特徴をチェックすれば、自身のどんな特性を役立てられるのか把握しやすくなります。具体的な特徴は、以下の4つです。
- コミュニケーション能力が高い
- 発想力が豊か
- 読書が好き
- 好奇心旺盛
①コミュニケーション能力が高い
コミュニケーション能力が高い人は、制作や出版をスムーズに進める上で重要な連絡や交渉を上手くこなせるため、出版社の業務に向いています。
営業の仕事では、相手のニーズを汲み取りつつ会社側の要望を通すことが必要になるため、相手から好感をもらえる接し方が重要になるのが特徴です。
また、業務は出版取次会社や書店など、さまざまな会社と関わりながら進めていく必要があります。
全体の管理を行いながら、適宜必要な連絡を素早く行えるスキルも必要です。
②発想力が豊か
発想力が豊かな人は、作品を世の中に知ってもらうための展開方法を考えたり、紙面のデザインをより見やすく華やかにしたりする業務で活躍できます。
発想力を仕事に活かせば、固定観念に囚われすぎずに新しい発想を取り入れて、魅力的な広告を作ったり作品とのコラボレーション企画を提案したりできるのが強みです。
著作者が手掛けた作品や最新のファッション情報を世の中に届ける仕事では、内容を理解して効果的にアピールする創造力も求められます。
③読書が好き
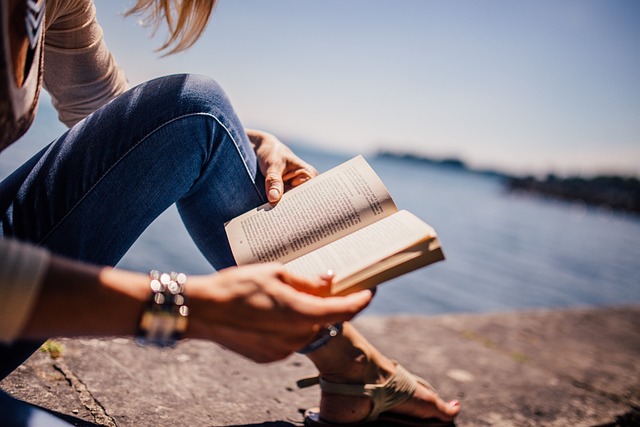
読書が好きな人は、モチベーションを高く維持しやすいため出版の業務に向いています。
これまで特定のジャンルの雑誌や書籍を読んできた経験があれば、読者としての目線も活用しつつ最適なデザインを考えられるのが強みです。
また、かつて読書を楽しんでいたからこそ作品の魅力に気付き、引き出す仕事に熱心に取り組めるといった利点もあります。
読書で作品を楽しんでいた経験を活用し、就活で実際に制作や出版に携わりたいと考えている、と熱意を強調できるのもポイントです。
④好奇心旺盛
好奇心旺盛な人は、IT技術やカフェなどとコラボした新しい分野の事業にも積極的に取り組めるため、仕事に向いています。
出版社が今後利益を増やしていくためには、新しい分野に進出していくことが求められるため、将来的にも活躍できるのが強みです。
また、世の中で流行していることやユニークな企画などの情報収集を自発的に行えるかどうかも、業務では重要になります。
さらに、書籍は先を見据えた内容を取り入れたものの方がニーズがあるため、一歩先を考慮した内容に仕上げられる人が向いているのも特徴です。
出版社に就職するためにやるべきこと4選
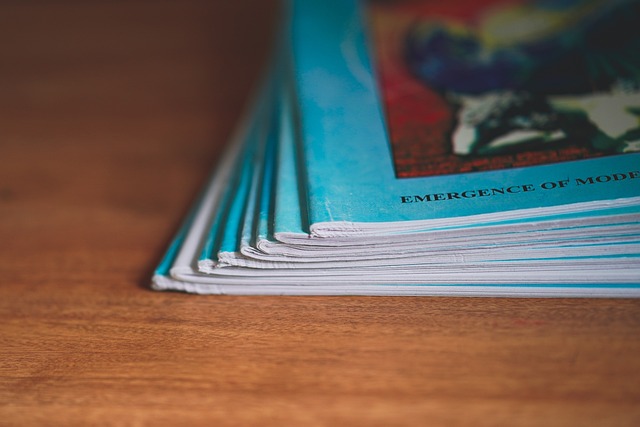
出版社に就職するためにやるべきことを把握していれば、就活に向けた対策を実践できます。やるべきことは、以下の4つです。
- インターンシップや説明会に参加して雰囲気を掴む
- 文章力を鍛える
- 志望する出版社の書籍や雑誌を把握しておく
- OB訪問で社員の声を聞く
①インターンシップや説明会に参加して雰囲気を掴む
インターンシップや説明会に参加すれば、業務内容の雰囲気を掴みやすくなります。
実体験として業務に関わった経験は、就活で説得力のある意見を伝えるために大いに役立つのがポイントです。
また、説明会はさまざまな企業が合同で開催しているものもあり、参加することで企業ごとの特色を比較しやすくなります。
インターンシップの選考に応募すれば、就活前に面接に慣れやすくなるのが利点です。
②文章力を鍛える
文章力を鍛えておけば、言葉を扱う仕事にスムーズに馴染めるのがメリットです。
正しい言葉遣いができていれば、文章表現をチェックしてより正しい表現に修正する業務でも活躍できます。
また、文章力を伸ばしておけば就活で論理的な文章を用いて自身のスキルを主張できるのもポイントです。
文章力をアップさせるには、ただ本を読むだけでなく自分で言語化する練習を積み、構成を考えてから文章を組み立てる習慣をつけることが大切になります。
③志望する出版社の書籍や雑誌を把握しておく

志望する出版社が手掛けている書籍や雑誌を実際に手に取って、どんな魅力があるのかを把握しておくことも大切です。
企業が展開している事業内容を確認するだけではなく、制作している作品の中身を理解することで、該当する会社で働きたいという熱意があることを強調しやすくなります。
就活へのモチベーションを高めるためにも重要な行動です。自分が業務を行う際にはどんな作風を重視したいと考えているのか、実践的な意見を持てます。
④OB訪問で社員の声を聞く
OB訪問で社員の声を聞けば、実際にどんなスケジュールで働いているのか、どんな点にやりがいを感じるのか聞いて参考にできるのがメリットです。
社員からどんな人材が求められているのか聞き出せれば、自身との共通点を見出し、面接で自分はどう活躍できるのかを強調して説明できます。
OB訪問をした経験を紹介すれば、仕事に向き合う社員の方の姿勢に憧れた、といった動機に説得力が増すのもポイントです。
【学歴フィルターあり】出版社への就職に有利な大学や学部系統

出版社はほとんど東京に本社を持っているため、東京の大学が有利になります。
また、就職者は東大や京大・早慶・難関国公立大など、偏差値が高い大学の出身者が多いため、学歴フィルターはあると判断可能です。
高い学歴を持っている学生が多く応募する分、学歴に自信が持てない場合一歩出遅れてしまうため、注意が必要になります。
企業が求める人材の条件を追求して、さらに踏み込んだ就活対策を行わなければいけません。
なお、どの学部でも出版社に就職はできるため、理系だから選考を通過できない、と就活を諦めなくともよいのがポイントです。
出版社への就職を目指すなら万全な対策を行おう
出版社への就職を目指すなら、万全な対策を行いましょう。
編集や制作・営業・デジタル化など、仕事内容への理解を深めた上で、仕事に活かせる自身の強みを探すのがおすすめです。
企業が発行している雑誌や書籍も手に取ってチェックして、志望度の高さを強調するために有効活用しましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









