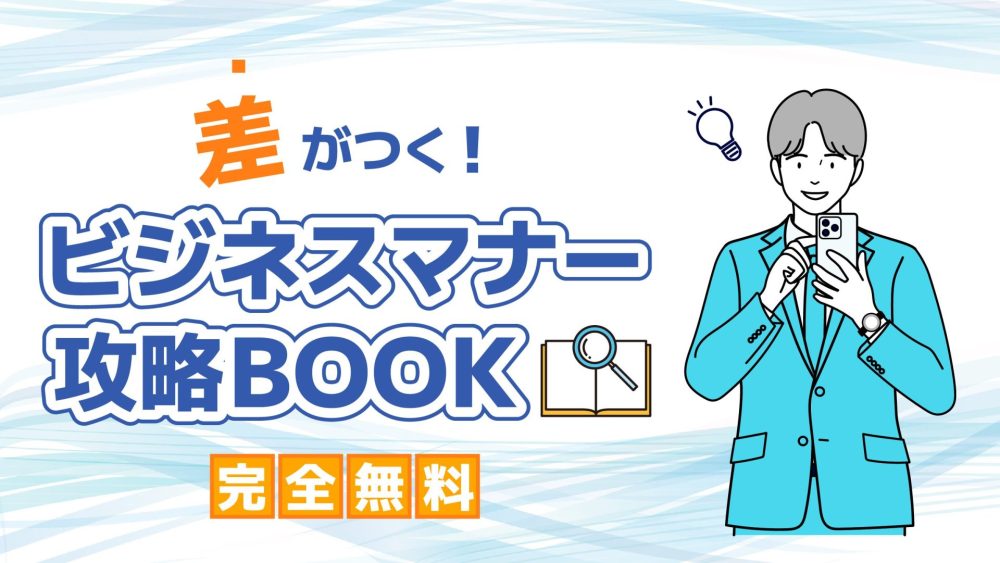選考を辞退しなければならなくなった場合、「連絡は面接日の直前でもいい?」と気になっている人もいますよね。結論、面接辞退の連絡は前日にしても問題ありません。
しかし、辞退の連絡だけでも気が重いうえ、どう連絡すれば失礼にならないのかがわからず、迷ってしまう方も多いでしょう。
そこで、本記事では面接前日に辞退を伝える時のマナーやポイント、注意点、例文などを詳しく解説します。基本的な方法を確認し、スムーズに連絡を終えるための参考にしてください。
全て無料!面接対策お助けツール
- 1実際の面接で使われた面接質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作成できる
- 3強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。
面接を前日に辞退する時のマナー4つ
まずは、連絡をする際に意識しておきたい4つのマナー紹介します。
- なるべく早めに連絡する
- 緊急性があるため電話をする
- 無断で辞退するのは禁物
- 営業時間内に連絡する
相手に失礼がないように、しっかりとマナーを守って辞退の連絡をしましょう。
明日、面接があるけど不安すぎる…
どんな質問が来るか分からず、緊張してしまう…
このように面接に対しての漠然とした不安から、面接に苦手意識を持ってしまったり、面接が怖いと感じてしまうこともありますよね。企業によっても面接の質問や内容が違うので、毎回ドキドキしてしまいます。
そんな就活生の皆さんのために、カリクル就活攻略メディアでは、実際に400社の面接の質問を調査し、100個の質問を厳選しました。LINE登録をすることで【完全無料】で質問集をダウンロードできます。面接質問集をゲットして、不安を解消した状態で面接に臨みましょう!
\LINE登録1分|400社の質問を厳選/
①なるべく早めに連絡する
担当者への連絡はできるだけ早くしてください。なぜなら、企業は貴重な時間を割いて面接のスケジュールを組んでくれているからです。
すでに辞退を決めているにも関わらず連絡をしないと、相手に迷惑をかけることになるでしょう。また「せっかくの準備が無駄になった」と担当者に不快感を与える可能性もあります。
意思が固まった時点ですぐに企業側へ連絡すれば、大きな迷惑をかけることはなくなるので、注意するようにしてください。
②緊急性があるため電話をする
企業への連絡は基本的にメールを使いますが、面接の前日・当日に連絡する時や、最終面接を辞退する時など、緊急性・重要性ともに高い場面では、すぐに電話で伝える必要があります。
メールを使うと相手が読むまでに時間がかかりやすく、場合によっては連絡に気づかず面接本番を迎えてしまう可能性もあるでしょう。
電話なら相手に直接辞退を伝えられるため、メールのように読み過ごす心配はありません。状況に合わせて、電話で連絡をするようにしてください。
③無断で辞退するのは禁物
全く連絡をせず、いわゆる「バックレ」で辞退するのは、絶対にやってはいけないマナー違反の1つです。連絡をしないままだと、面接官は当日無駄な時間を過ごすことになります。
無断辞退は、面接のためにスケジュールを空け、準備を整えてくれた人に対してとても失礼な行為だと言えるでしょう。
面倒になったり、気まずさを感じたりすることもありますが、きちんと自分の意思を伝え、相手に迷惑をかけないことは社会人として当然です。必ず連絡をするようにしてください。
④営業時間内に連絡する
社会人の基本マナーとして、時間内の連絡を意識することも大切です。営業時間外に連絡をしても、担当者はすでに退社している可能性があります。
仮に退社していなかったとしても、営業時間外の連絡は良い顔をされません。「ビジネスマナーが備わっていない」とマイナスイメージを持たれる可能性も。
面接前日に辞退の連絡をする場合、営業時間を確認した上で遅れないように電話をしてください。
また、昼休憩中や、退社準備で忙しい営業時間終了直前も連絡を避けた方が良いと言われているため、注意が必要です。
前日に面接辞退連絡をする時のポイント2つ

ここでは、前日に辞退を伝える際に意識したい2つのポイントを紹介します。
- 先に要件を簡潔に伝える
- 言い訳に聞こえる理由は言わない
適切な伝え方を知らないと、相手に失礼な印象を与える可能性があるため、各ポイントを踏まえた上で連絡しましょう。
①先に要件を簡潔に伝える
前日に辞退の連絡をする際は、まず要件を簡潔に伝えることが大切。要件から話さないと、何のために連絡したのか理解してもらいにくいからです。
「いきなり辞退の旨を伝えるのは気まずい」と感じている場合、つい理由から話してしまいがちですが、要点を得ない話は逆に相手に迷惑をかけてしまいます。
電話をする際は、相手の貴重な時間を使っていることを忘れずに、伝えたい内容をまとめるようにしてください。
②言い訳に聞こえる理由は言わない
辞退の理由を答える際は、言い訳に聞こえるような話を長々としないことも重要なポイントです。
「辞退をするのは申し訳ない」という気持ちが強いと、さまざまな言い訳をしてしまいがちですが、仕事中の相手にとって長話は迷惑でしかありません。
要件を伝えるときと同様に、なぜ辞退をするのか簡潔に伝えるようにしてください。
電話をする前に辞退の理由をまとめ、落ち着いて話せるように準備しておくと、言い訳めいた長話になるのを防げるでしょう。
前日に面接辞退する時に使える理由一覧

ここからは、辞退をする際に使える理由の代表例を6つ紹介します。
- 一身上の都合によるもの
- 他社から内定をもらった
- 日程が被った
- ケガや病気
- 社風とマッチしないと考えた
- スキル不足を感じた
それぞれの理由の詳細を確認し、辞退の連絡をする際に役立ててみてください。
①一身上の都合によるもの
明確な理由を明かしたくない場合におすすめなのが「一身上の都合によるもの」という答え方です。
一身上の都合とは個人的な都合や問題のことを表し、辞退の連絡以外にもさまざまな場面で活用できます。
ただし「一身上の都合で辞退をしたい」と伝えた場合も、企業によっては「よろしければ具体的な理由を聞かせていただけませんか?」と質問される時もあるでしょう。
そのため、一身上の都合以外に相手が納得してくれる理由を用意しておくと安心です。
②他社から内定をもらった
面接予定の企業ではなく、内定をもらった他社に入社すると決めた場合は、辞退の旨を伝えた上できちんと謝罪の気持ちを伝えることが大切です。
また、よく考えた末に出した結論であることを明確に伝えるのもポイント。
同業界の他社に入社する場合、社会人になってから何らかの接点を持つ可能性が高いため、失礼な態度をとると後々の関係にヒビが入ることがあります。
相手に失礼だと思われないよう、細心の注意を払いながら伝えてください。
③日程が被った
選考の日程が被り、他社の面接を受けることを選んだ場合は、日程が被った旨を正直に伝えましょう。
この場合「日程の都合がつかなくなった」と伝える程度で問題はなく、都合がつかない理由を具体的に説明する必要はありません。
もし、相手から詳細な理由の説明を求められた時は、他社と選考が被ったことを伝え、丁寧に謝罪の気持ちを伝えましょう。
なお、企業側で日程調整が可能な場合は引き止められる可能性があるため、これ以上選考を受ける意思がないのであれば、その旨をはっきり伝えることも大切です。
④ケガや病気
ケガや病気を患った場合は、現時点での体調や医者からの指示について触れ、辞退する旨を伝えましょう。
具体的な病名を答えたくない場合は濁しても差し支えありませんが、誠意を持って謝罪の気持ちを伝えるようにしてください。
ただし、日程の都合が合わない場合と同様に、企業側で調整が可能な場合は引き止められる可能性があります。
他社の選考を優先したり、内定が出たりしたことを隠して病気やケガを辞退の理由にすると、嘘が発覚した際に不誠実な印象を与えるため、本当の理由を伝えることが大切です。
⑤社風とマッチしないと考えた
企業の社風とマッチしないと感じて選考を辞退する場合、伝え方に注意する必要があります。
企業側から見れば「まだ入社もしていないのに、自社の何がわかるのか」と不快感を与える可能性があるからです。
そのため「社風にマッチしないから辞退する」とストレートに伝えるのは避けましょう。
例えば「企業研究を深める中、自分が求める環境との違いに気づき、再度検討した結果、辞退する結論になった」といったように婉曲表現を意識するのがポイントです。
⑥スキル不足を感じた
選考を受ける中でスキル不足を感じ、面接を辞退することになったら、その旨を明確に伝えてください。
また「前回、面接を受けた際に企業の雰囲気が悪かった」「インターネットの口コミが悪い」など、伝えづらい理由がある場合も、スキル不足を理由にすれば相手に伝えやすいでしょう。
マイナスイメージを抱いていることを企業側に伝えると、不快感を与える可能性が高まります。「スキル不足の自分に非がある」という表現にすれば、大きな問題にはならないはずです。
前日に面接辞退をする時の例文|電話・メール別

ここでは、連絡の仕方に迷ったときに役立つ2つの例文を紹介します。
- 【電話編】面接辞退例文
- 【メール編】面接辞退例文
電話とメールとでは伝え方が異なるため、具体的な内容を確認した上で、相手に失礼がないよう連絡していきましょう。
【電話編】面接辞退例文
電話での連絡は、最初に通話の時間を割いてもらうことに対して謝罪の意を示すのがポイントです。また、想像以上に緊張する可能性もあるので、伝えることをメモにまとめておくのがおすすめです。
| お世話になっております。△月△日△時に面接予定の××と申します。お忙しいところ、突然の連絡となり申し訳ありません。ただいま、お時間はよろしいでしょうか? 大変恐縮ですが、志望企業様より内定の連絡を受けたため、熟考した結果、この度の面接は辞退させていただきたいと考えております。 せっかく選考のお時間を割いていただいたにも関わらず、このような結果となり申し訳ございません。 本来であれば、直接貴社に伺ってお詫び申し上げるべきところ恐縮ですが、面接前日ということもあり、電話での連絡とさせていただきました。 こちらの都合で直前の連絡となり、大変申し訳ございませんでした。重ねてお詫び申し上げます。 この度は、貴重なお時間ありがとうございました。それでは、失礼いたします。 |
【メール編】面接辞退例文
メールで辞退の旨を伝える場合は、件名で要点が分かるようにします。例えば「面接辞退のご連絡:××××(名前)」と記載すると良いでしょう。また、簡潔に分かりやすく伝えることも意識してください。
| △△株式会社 △△部 ××様 お世話になっております。◯月◯日◯時より面接のお時間をいただいております、××と申します。 突然のことで大変恐縮ですが、この度は一身上の都合により面接を辞退させていただきたくご連絡申し上げました。 ご多忙の中、貴重な時間を割いて選考を進めていただいたにも関わらず、大変申し訳ありません。このような結果になってしまったこと、お詫び申し上げます。 本来であれば貴社にお伺いして直接お詫び申し上げるところですが、メールによるご連絡となってしまい、大変申し訳ございません。 末筆ながら、貴社の益々のご発展を祈念申し上げます。 ××××(名前) 〒△△△-△△△ ◯◯県◯◯市△-△-△△(住所) 080-△△△△-△△△△(電話番号) △△△△△△@.com(メールアドレス) |
前日に面接辞退をする時の注意点2つ

ここからは、辞退の連絡をする際に意識したい2つの注意点を紹介します。
- 辞退しても後悔しないか考える
- 再応募はできない
どのような点に注意すべきかしっかりと確認した上で、冷静に判断を下すようにしましょう。
①辞退しても後悔しないか考える
辞退の連絡をする際は、本当に後悔しないかよく考えることが重要です。
選考の日程が被ったり、内定をもらったりして他の企業を優先しようと考えている場合は、その企業が自分に合っているのか熟考する必要があります。
企業研究を深めた結果、実は辞退しようとしている企業の方が相性が良かった、という場合も考えられるので、よく検討するようにしてください。
面接の辞退が今後の人生を左右する大きなターニングポイントになる可能性もあることを考慮に入れ、冷静な判断を下しましょう。
②再応募はできない
面接を辞退した後に、同じ企業に再応募をするのは難しいと言われています。軽い気持ちで辞退をすると、後戻りはできないので注意してください。
例えば、他社との日程被りや体調不良などで面接を受けるのが難しくなった場合、事情を説明すれば日程調整をしてくれる可能性があります。
辞退すべきか迷っている場合は、日程を変更できないか聞いてみるのがおすすめです。
「この企業に入社することは絶対にない」という確信が持てないのであれば、できるだけ辞退をしない方が懸命でしょう。
前日の面接辞退に関するよくある質問2つ

最後に、面接辞退に関してよくある2つの質問を紹介します。
- メールの返信・電話の応答がない場合は?
- 企業から返信が来たら、返すべき?
辞退を検討する際には、「こういう場合はどうすれば?」と疑問が湧きがちですよね。主な質問と回答を確認して、疑問を解消してください。
①メールの返信・電話の応答がない場合は?
電話の場合、担当者からの応答がなければ当日中にもう一度連絡をしましょう。
二度目の電話でも応答がない時は、電話に出た社員に連絡をしたことを伝えてもらい、相手から返答があるのを待ってください。
メールの場合、返信がなければ電話で連絡し、辞退の旨を伝えることが大切です。面接前日は準備に追われることが多いため、担当者はメールを見ていない可能性があります。
相手がメールを見ないまま当日を迎えてしまうと、無断欠席したと思われるリスクもあるため、電話で確認しておくと安心です。
②企業から返信が来たら、返すべき?
電話やメールで辞退する旨を伝えた後は、企業側からメールなどで返信が来ても連絡を返す必要はありません。
企業側が面接の辞退を了承し、要件が済んだのであれば、再び連絡を返すことで相手の貴重な時間を奪ってしまう可能性があります。
企業側からの返信があった時点で、連絡のやり取りは終了したと考えましょう。
もし、返信をしないままでいることがどうしても気になるのであれば、メールで返信しても良いですが、短文で簡潔に伝えるようにしてください。
前日に面接辞退をしても大丈夫!例文を参考に電話をかけよう
面接の辞退を決めたらなるべく早く伝えることが大切ですが、前日に連絡しても問題はありません。
緊急性・重要性の高い内容なので、電話を使って要件を簡潔に伝えることが大切です。
貴重な時間を割いてくれたことへの感謝と謝罪の気持ちも添えて、トラブルなく辞退の連絡を終えるようにしましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。