総合商社とは?専門商社との違いや仕事内容・代表企業を徹底解説
就職活動の志望企業として、総合商社を目指す人も多いでしょう。しかし「総合商社って何?専門商社と何が違うの?」と悩みますよね。
そこで本記事では、総合商社について徹底解説します。専門商社との違いや仕事内容、代表企業も紹介しているのでぜひ最後まで読んでみてくださいね!
企業分析をサポート!便利ツール集
- 1適性診断|企業研究
- ゲットした情報を見やすく管理!
- 2志望動機テンプレシート|楽々作成
- 企業に合った志望動機がすぐに書ける!
- 3志望動機添削|プロが無料添削
- LINEで完結|志望動機をもっと好印象に!
総合商社とは?

総合商社とは、さまざまな分野の商品やサービスを扱い、世界中の企業やプロジェクトを結びつける企業のことです。日本独自のビジネスモデルとして知られており、就職先としても非常に人気があります。
まずは、総合商社の本質をしっかりと理解しておくことが大切です。総合商社は、単にモノを売買する企業ではありません。
食品やエネルギー、金属資源、機械など多岐にわたる分野で取引を行い、国内外の企業と連携しながら事業を展開しています。
商取引だけでなく、出資や事業投資を通じて、新たなビジネスの立ち上げにも深く関わる点が大きな特徴です。
たとえば、海外で資源開発を行う企業に出資し、そのプロジェクト全体をサポートするようなケースもあります。
このように、単なる貿易会社とは異なり、総合商社は事業開発や経営支援、プロジェクト推進など幅広い業務を担っています。
そのため、「商社=貿易会社」とイメージしていると、企業の実態を正確に理解できないかもしれません。
志望動機や面接で自分の考えをしっかり伝えるには、業界の構造や各企業の役割について深く知っておく必要があるでしょう。
総合商社の主な事業内容とは

総合商社は多様なビジネスを展開しており、単なる「貿易会社」ではありません。中心となるのは、トレード・事業投資・事業経営の3つの分野です。
ここでは、それぞれの内容について分かりやすく紹介します。
- トレード
- 事業投資
- 事業経営
①トレード
トレードは総合商社の原点にあたる事業で、もっとも基礎的かつ重要な役割を果たしています。世界中で資源や製品を調達し、それを必要とする市場へ流通させることが主な目的です。
たとえば、中東の原油を日本へ輸入したり、日本の建設機械を東南アジアへ輸出したりと、国をまたぐ取引が日常的に行われています。
一見すると、単なる輸出入の仲介に思えるかもしれませんが、商社のトレードは非常に高度です。
商品の仕入れから販売までの間に、為替変動や物流リスク、法規制の違いなど、さまざまな課題が立ちはだかります。
これらをコントロールしながら、適切な利益を確保するためには、緻密な計画と柔軟な判断が必要です。
さらに、商社は単なる取引の実行者ではなく、取引先との長期的な関係構築や新たなビジネスのきっかけを生み出すハブとしても機能しています。
特に近年では、トレードを通じて得られた市場情報をもとに、次の事業投資や新規事業の立ち上げにつなげるケースも増えています。トレードは今なお、商社の成長の原動力となっているのです。
②事業投資
事業投資は、商社が企業やプロジェクトに出資し、その利益の一部を得るビジネスモデルです。しかし、それだけではありません。
商社は出資先の企業や事業の成長に深く関与し、単なる資金提供者を超えた役割を担っています。
たとえば、海外の水力発電プロジェクトに出資して、その運営体制や長期的な収益モデルの設計に関わることもあります。
このような投資活動の特徴は、いわゆる「ファンド型の投資」とは異なり、商社が自ら現場に足を運び、ビジネスの本質を見極めながら関与していく点にあります。
たとえば、新興国のインフラ事業では、政治リスクや通貨リスクが高く、表面的なデータだけでは意思決定できません。こうした場面で、商社の経験や人脈が活かされるのです。
また、事業投資は商社にとって重要な収益の柱であり、長期的かつ安定した収益を生み出す仕組みとして機能しています。
市場の景気変動に左右されやすいトレードと比較して、比較的安定性がある点も特徴でしょう。だからこそ、商社では財務的な視点と事業全体を俯瞰する力がバランスよく求められます。
単なる資金運用ではなく、実業の一環として投資に取り組むスタイルが、商社の投資事業の強みといえるでしょう。
③事業経営
事業経営は、商社が出資先やグループ企業の運営に深く関与するフェーズであり、経営における意思決定にも携わる重要な役割です。
たとえば、総合商社が食品会社に出資した場合、その商社の社員が役員として常駐し、原材料調達から販売戦略までを一貫してサポートすることがあります。
これは、単なるオブザーバー的立場ではなく、経営の一員として実務に関わるということです。事業経営の場では、マネジメント能力だけでなく、現地の文化や商習慣に対する理解も欠かせません。
たとえば、海外の製造会社を運営する際には、現地の雇用慣行や労働法制に対応しながら、効率的な生産体制を築く必要があります。
こうした課題に直面することで、商社マンは経営者としての視点と感覚を自然と身につけていきます。加えて、商社における事業経営は、企業価値の最大化を目指すという明確な目的を持っています。
そのため、収益性や業務効率を高めるための施策を自ら立案し、現地スタッフとともに実行に移していく機会が多くあります。
若手社員が早い段階からプロジェクトの中心を担うことも珍しくなく、自分の判断や行動が経営に直結するやりがいを感じられるでしょう。
このように、事業経営は単なる経済活動を超え、ヒト・モノ・カネを動かしながら事業を成長させるダイナミズムに満ちています。
商社で働くことによって、世界規模で経営に携わる経験が得られるのは、大きな魅力といえるでしょう。
総合商社での職種と仕事内容を解説

総合商社では、多様な職種が存在し、それぞれの役割がビジネスの基盤を支えています。就活生にとって、自分に合う仕事を見極めるためにも、各職種の特徴や業務内容を理解することが重要です。
ここでは、総合商社での代表的な職種について紹介します。
- 営業職
- 企画職
- 事務職
- 総合職と一般職
- 経理・財務職
- 法務・コンプライアンス職
- 人事・総務職
- IT・DX推進職
「自分に合う仕事は何だろう….」
「やりたい仕事なんてな….」
自分のやりたいことや合う仕事が分からず、不安な気持ちのまま就活を進めてしまっている方もいますよね。カリクル就活攻略メディアでは、就活応援のために「適職診断」を用意しました。LINE登録して診断するだけであなたに向いている仕事や適性が分かります。3分で診断結果が出るので、就活に不安がある方は診断してみてくださいね。
① 営業職
営業職は総合商社の中でも特に注目される職種であり、事業の最前線で活躍します。
扱う商材はエネルギーや食料、インフラ機材など多岐にわたっており、単なる物の売買にとどまらず、事業投資やプロジェクトマネジメントに関わることも珍しくありません。
たとえば、発展途上国での電力開発プロジェクトでは、現地政府との契約交渉や資金調達、インフラ整備を行う企業との連携が不可欠です。
その際、語学力やプレゼン力といった表現力に加え、政治的リスクや為替変動といった外部要因を予測する能力も求められます。
業務の幅が広く、専門知識が必要な分野も多いため、入社後に各業界への深い理解を培う姿勢が重要です。
時差や文化の違いによる調整も日常的に発生するため、柔軟に対応できる力とストレス耐性も問われるでしょう。華やかなイメージの裏には、緻密な計画と粘り強い交渉力が支えになっています。
② 企画職
企画職は、総合商社において未来の事業を創造する役割を担っています。新規事業の立案や既存事業の再構築、M&Aの検討など、戦略的な意思決定の根幹を支える仕事です。
短期的な利益ではなく、5年後10年後を見据えた長期的視点が求められます。主な業務には、国内外の市場動向の調査、事業モデルの構築、関係各所との交渉などが含まれます。
新しいプロジェクトを始動する際は、収益性の試算や法務・財務の観点からの整合性確認など、多角的なアプローチが必要です。
また、既存事業の抜本的な見直しに着手することも多く、時にはリストラクチャリングや事業撤退の判断を下す場面もあります。
こうした場面では、論理的思考と同時に冷静かつ公平な判断力が不可欠です。日々変化するビジネス環境の中で、チャンスを見逃さず掴むためには、情報感度と大胆な発想が必要でしょう。
裏方のように見えるポジションですが、会社の方向性に大きく関与する、非常に影響力のある職種です。
③ 事務職
事務職は、商社の業務が円滑に進行するための「縁の下の力持ち」として機能しています。
具体的には、契約書や請求書の作成、営業部門のスケジュール調整、社内システムへのデータ入力など、多岐にわたる業務をこなします。
業務の正確性が重視されることは言うまでもありませんが、それだけではありません。近年では、業務プロセスの見直しや効率化の提案など、能動的な姿勢が求められる場面も増えています。
たとえば、RPA(業務自動化ツール)を導入する際には、実務を深く理解している事務職の意見が反映されることが多くなっています。
また、社内の情報共有のハブとしての役割も大きく、他部署との連携やサポート力も重要です。組織の潤滑油となる存在として、信頼を得られるかどうかがキャリアにも直結します。
安定的に働き続けやすい点や、ライフイベントとの両立がしやすい点も事務職の魅力でしょう。裏方でありながら、多くの人の働きを支えている実感を得られる仕事です。
④ 総合職と一般職
総合商社では、キャリア形成に直結する2つの職種区分「総合職」と「一般職」が設けられています。総合職は全国および海外転勤があるのが前提で、将来の経営幹部候補としての教育が行われるポジションです。
営業や企画、海外赴任など幅広い業務経験を積みながらステップアップしていきます。一方、一般職は転勤がなく、主にサポート業務に従事します。
部署によっては専門性の高い業務を任されることもあり、必ずしも総合職の補助という立場にとどまらないケースも見られます。
最近では、働き方の多様化により、職種間の垣根が柔軟になりつつあります。たとえば、一般職でも業務の幅が広がり、企画や調整を担うケースも出てきています。
その一方で、ライフスタイルやキャリアビジョンに応じて職種変更を希望する人も増えています。
どちらを選ぶかは、自身の価値観と将来像に大きく関係してきます。どのような働き方を望むのか、自分に問いながら職種選びをすることが大切です。
⑤ 経理・財務職
経理・財務職は、企業の財務的な健全性を保つために欠かせない存在です。商社のように多額の取引や投資を行う企業では、数字の管理が極めて重要となります。
売上や費用の管理、決算業務、税務処理といった基本業務に加えて、資金繰りの調整や投資案件の収益シミュレーションまで幅広く担当します。
たとえば、海外プロジェクトへの出資では、現地の会計制度や為替リスクを考慮しながら収支を予測しなければなりません。
このような状況では、正確な計算能力だけでなく、先を見通す分析力や国際的な視野も求められます。
また、財務部門では社内の意思決定を数字で裏付ける役割も果たしており、経営層からの信頼も厚いポジションです。
その分プレッシャーは大きく、ミスが許されない場面も少なくありません。だからこそ、責任感の強さや丁寧な仕事ぶりが評価されやすい傾向にあります。
数字が得意というだけでなく、論理的に物事を考える力や、地道な作業を厭わない姿勢がある人には向いているでしょう。
将来的には海外拠点での勤務や国際会計基準への対応など、グローバルな活躍も期待できます。
⑥ 法務・コンプライアンス職
法務・コンプライアンス職は、企業が健全かつ合法的に活動できるように支える専門職です。
主な業務は契約書の作成・確認、訴訟対応、知的財産権の管理、社内規定の整備、コンプライアンス教育などです。
特に総合商社では海外取引も多いため、各国の法制度や条約に精通しておく必要があります。
たとえば、新興国での資源開発プロジェクトでは、現地政府との契約に加え、労働法や環境規制への対応も求められます。
こうした背景に対応するためには、法的知識だけでなく、ビジネス全体の流れや商習慣への理解も重要です。さらに、社内のコンプライアンス意識を高めることも役割のひとつです。
違法行為や不正が発生するリスクを未然に防ぐには、社内教育やチェック体制の整備が欠かせません。そのためには、他部署との調整や説得力ある説明を行うコミュニケーション力も必要でしょう。
単なる法的サポートではなく、ビジネスパートナーとして現場を支える姿勢が求められます。細部へのこだわりと、全体を見る視点の両方を持ち合わせた人材が重宝される職種です。
⑦ 人事・総務職
人事・総務職は、企業の人的資源や組織運営を支える重要な存在です。
新卒や中途の採用活動、社員教育、評価制度の設計と運用、労務管理、オフィス環境の整備、福利厚生の導入など、その業務範囲は多岐にわたります。
たとえば、新卒採用を担当する場合は、会社説明会の運営や面接官との日程調整だけでなく、応募者の志望動機や適性を見極める力も問われます。
また、研修制度の設計では、事業部門と連携して実務に即したプログラムを考案する必要があります。
総務部門では、社内の備品管理からBCP(事業継続計画)の策定まで担当し、社員が安心して働ける環境づくりを推進します。こうした仕事には、調整力や問題発見力、そして実行力が求められます。
人事・総務は、会社の「人と仕組み」に関わるため、企業文化や価値観にも深く影響を与えるポジションです。
自分の対応次第で職場の雰囲気や社員のモチベーションが変わるという責任とやりがいがあるでしょう。
人と接することが好きで、組織全体を良くしていきたいという思いを持つ方には、非常に適した職種といえます。
⑧ IT・DX推進職
IT・DX推進職は、企業のデジタル変革を支える新しい職種として注目を集めています。
総合商社では、伝統的なビジネスをテクノロジーによって進化させることが求められており、IT・DXの推進は企業の競争力に直結するテーマとなっています。
業務の中心は、社内システムの構築・運用、データ分析の支援、AIやIoTといった先端技術の活用、新規事業でのデジタルソリューションの導入などです。
営業部門の業務効率化や、物流の最適化、リスク管理の高度化といった形で具体的な成果を上げることが期待されています。
この職種には、単なる技術者ではなく、現場の課題を正しく把握し、最適なソリューションを提案できる力が必要です。
ITスキルに加えて、課題発見力、説明力、そして関係者を巻き込む推進力が問われる場面も多くあります。
また、理系出身者だけでなく、文系であってもテクノロジーに関心があり、論理的に物事を考える力があれば十分に活躍できます。
総合商社が今後さらに成長していくために欠かせない職種であり、自ら変化を起こしたいという意欲を持つ方には最適です。
総合商社の課題

グローバルな舞台で活躍する総合商社には、華やかなイメージがあります。しかし実際には、国際競争の激化や事業リスクの増加、環境問題やデジタル化への対応など、多くの課題に直面しています。
これらの背景を理解しておくことは、就職活動において他の学生と差をつける大きなポイントになります。ここでは、総合商社が抱える課題について詳細に説明します。
- 国際競争の激化と差別化の必要性
- 事業リスクとリスクマネジメント体制
- 環境問題とサステナビリティ対応
- DX化や業界構造改革への対応
① 国際競争の激化と差別化の必要性
総合商社は、これまで長く続いてきた既存の枠組みの中で優位性を保ってきましたが、今では状況が大きく変わっています。
新興国の企業が成長を遂げ、テクノロジー系企業が新たな商流を生み出しており、競争の舞台は一層広がっています。これにより、従来のやり方では通用しない場面が増えつつあります。
そのため、各商社は独自性や強みを明確に打ち出す必要があります。たとえば三菱商事は、再生可能エネルギー分野に積極的に取り組むと同時に、食品・物流など非資源ビジネスへの比重を高めています。
また住友商事は、インフラや医療関連事業に注力することで、新たな市場価値を築こうとしています。こうした変化の背景を理解することは、単なる企業分析にとどまりません。
志望動機や面接での受け答えにおいて、どの商社がどんな戦略を取っているのかを語れることが、深い理解の証となります。
時代の潮流を的確にとらえ、企業が何を求めているのかを先読みできる学生こそが、採用の現場でも注目されるでしょう。
② 事業リスクとリスクマネジメント体制
総合商社は、世界中の多様な分野にビジネスを展開しているため、経済、政治、自然災害など、あらゆる外部要因によるリスクにさらされています。
国や地域によって事情が異なり、一つの出来事が連鎖的に収益全体に影響を及ぼすこともあります。そのため、商社は常にリスクの「予測」と「分散」を意識した行動を取らなくてはなりません。
たとえば、エネルギー関連事業であれば原油価格の乱高下、食料事業であれば世界的な天候不順や輸送コストの増加がリスク要因になります。
さらに、地政学的な問題、為替の変動、政治的な規制強化など、商社が直面するリスクは複雑で多層的です。
これに対応するため、各社はAIやデータ分析ツールを活用したリスク予測システムを導入し、リアルタイムで状況を把握しています。
また、現地法人との連携を強化することで、地場情報の収集力も高めています。こうした取り組みは、単なるトラブル回避にとどまらず、ビジネスチャンスの発見にもつながる重要な基盤です。
商社を志望する学生にとっては、リスクを避けるだけでなく、どう活用するかという「攻めの姿勢」も求められます。多角的な視野を持ち、変化を前向きに受け入れる力が評価されるでしょう。
③ 環境問題とサステナビリティ対応
総合商社は、環境問題への取り組みが今や事業の存続に直結する時代に突入しています。
特に気候変動や地球温暖化といったグローバルな課題に対し、企業がどのように向き合うかが投資家や取引先から厳しく問われるようになりました。
これは単なるCSRの枠を超えた、経営そのものの再設計とも言えるでしょう。
たとえば伊藤忠商事は、脱炭素社会を見据えた「サステナビリティ戦略」を打ち出し、2030年までに特定資産のCO2排出量を半減させる計画を公表しています。
三井物産は、風力発電やEV(電気自動車)分野への出資を進めるなど、事業ポートフォリオの大転換に取り組んでいます。
さらに、近年ではESG(環境・社会・ガバナンス)への対応が、金融市場での信用力にも直結しています。サステナビリティに無関心な企業は、資金調達が困難になる可能性もあり、まさに死活問題です。
商社に関心のある学生は、こうした取り組みに対して自分がどのように関与し、貢献できるかを具体的に考えておく必要があります。環境への配慮が、ビジネスの成長とどのように両立できるのか。
その視点が、企業選びにも自己PRにも大きな違いを生み出すでしょう。
④ DX化や業界構造改革への対応
デジタル化の波は商社の業界構造を根底から変えつつあります。従来の総合商社は、人脈や現地での交渉力に大きく依存するビジネススタイルが主流でしたが、今ではそれだけでは不十分とされています。
ビッグデータやAIを活用し、商流・物流・投資判断までもシステムで最適化する時代が到来しています。たとえば、丸紅はDX人材の育成を急ピッチで進め、社内でのデジタル研修制度を整備。
グループ全体でのデータ活用を通じ、新しい収益モデルを構築しています。
双日はスタートアップとの連携を通じて、アグリテックやヘルステックといった分野にも参入しており、従来の枠組みを超えた挑戦を続けています。
このような動きは、単なる業務効率化ではありません。意思決定のスピードと正確さを劇的に高め、新しいビジネスチャンスを発見する力へとつながります。
つまり、デジタル技術が「攻め」の武器として使われているのです。就職を目指す立場としては、ITスキルを持っていること自体よりも、それをどう業務や戦略に活かせるかを語れることが重要です。
「商社にとってのDXとは何か」を自分の言葉で表現できるようにしておくと、面接でも大きなアピールにつながるでしょう。
5大商社とは?それぞれの特徴

総合商社といえば、多くの学生が思い浮かべるのが「5大商社」です。これは、三菱商事・三井物産・伊藤忠商事・住友商事・丸紅の5社を指します。
いずれも国内外で圧倒的な存在感を放ち、就活市場でも人気が高い企業ばかりです。それぞれの商社には明確な特徴があり、自分の志向や将来像に合った選択が大切です。
ここでは、5大商社それぞれの特徴について具体的に紹介します。
- 三菱商事|総合力と安定した収益基盤
- 三井物産|多角的事業展開と資源ビジネスの強さ
- 伊藤忠商事|生活消費分野での圧倒的な成長力
- 住友商事|幅広い分野でのバランス経営
- 丸紅|非資源分野での積極的な戦略展開
① 三菱商事|総合力と安定した収益基盤
三菱商事は、総合商社の中でも圧倒的な「総合力」と「安定性」で知られています。
エネルギー、金属、化学、機械、食品など10を超える事業グループを有し、それぞれが独立して利益を生み出せる体制を築いていることが強みです。
グローバル展開も積極的で、世界中に拠点を持ち、現地のパートナー企業と長期的な関係性を構築する力にも定評があります。
また、ポートフォリオ経営と呼ばれる分散型戦略を通じて、特定の業界や地域に依存せずにリスクを管理できる仕組みが整っています。
このため、不況時や市場の変化にも柔軟に対応し、利益を安定して確保できるのです。
就活生にとっては、長く安定したキャリアを描きやすく、自身の志向や専門性に応じて多彩な分野にチャレンジできる魅力があります。成長と安定の両立を望む人には最適な環境といえるでしょう。
② 三井物産|多角的事業展開と資源ビジネスの強さ
三井物産は、総合商社の中でも特に「多角化」と「資源ビジネスの強み」に注目されています。
とくに鉄鉱石、原油、LNG(液化天然ガス)などの資源関連で世界的な権益を有しており、海外企業と連携した大規模な資源開発を多数手がけています。
これらの資源は長期契約を通じて安定収益を生み出し、経営基盤を支えています。一方で、資源に偏らない柔軟な事業戦略も同社の魅力です。
ヘルスケア、インフラ、モビリティ、ICTなど、新興分野にも積極的に取り組み、次世代を見据えたビジネスモデルを構築しています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)やスタートアップ投資にも注力し、革新的な取り組みで競争力を維持しています。
このような幅広い分野への関与は、ひとつの業界や技術に縛られないキャリア形成を可能にします。変化を楽しみ、社会の動向に敏感な人にとっては、刺激的で学びの多い環境でしょう。
③ 伊藤忠商事|生活消費分野での圧倒的な成長力
伊藤忠商事は、「衣・食・住」に関わる生活消費分野で圧倒的な存在感を放つ総合商社です。
ファミリーマートを中心とした流通ネットワークをはじめ、食品、アパレル、日用品など、人々の日常生活に直結する分野を得意としています。
この分野では市場の動きが早いため、スピード感をもって戦略を実行できる組織体制が整っているのも大きな特長です。
また、消費者の行動やニーズを読み取るマーケティング力に優れており、国内外で収益を拡大し続けています。
生活に根ざした分野だからこそ、社会課題の解決にも直結しやすく、自身の仕事が誰かの役に立っていることを実感しやすいのもポイントです。
加えて、他商社に比べて非資源分野への依存度が高く、経済情勢の変化に柔軟に対応できる構造を持っています。
人々の暮らしを支える仕事に魅力を感じる人や、実感のあるビジネスに携わりたい人にとっては、やりがいの大きいフィールドといえるでしょう。
④ 住友商事|幅広い分野でのバランス経営
住友商事は、全方位型のバランス経営を実践する総合商社です。エネルギーやインフラといった大規模案件から、リテールや通信といった身近な分野まで、幅広く事業を展開しています。
とくに注目すべきは、過度な特定領域への依存を避けつつ、収益性と社会貢献性を両立する企業方針です。
経営の根底には「信用を重んじ確実を旨とする」という住友の事業精神があり、長期的視野に立った経営判断が重視されています。
そのため、時流に流されずに堅実に成長を遂げており、業績も比較的安定しています。コロナ禍や世界的な情勢不安の中でも回復力を発揮できたのは、この方針の賜物でしょう。
社内には誠実で穏やかな雰囲気があり、じっくりと成長を重ねたい人に合った職場文化です。華やかさやスピード感よりも、地道に実力を蓄えて長く働きたいと考える人には、とても相性が良い企業といえます。
⑤ 丸紅|非資源分野での積極的な戦略展開
丸紅は、非資源分野に力を入れている点で他の商社と一線を画しています。とくにアグリビジネス、発電、再生可能エネルギー、リース・金融など、今後成長が期待される分野への投資が目立ちます。
成長分野でのポジション確立を目指し、将来の収益源を多角的に育てている姿勢が印象的です。一方で、柔軟でスピード感のある意思決定も丸紅の特長です。
スタートアップとの連携や社内ベンチャー支援にも取り組んでおり、社員一人ひとりの挑戦を後押しする風土が形成されています。
過去には地味な印象を持たれていましたが、近年では革新的な企業として注目が高まっています。若手に対しても早い段階で裁量を与える文化が根づいており、自分のアイデアを実現しやすい環境です。
既存の枠にとらわれず、スピードと柔軟性を重視して働きたい人にとっては、最適なフィールドといえるでしょう。
総合商社に内定するためにやるべきこと
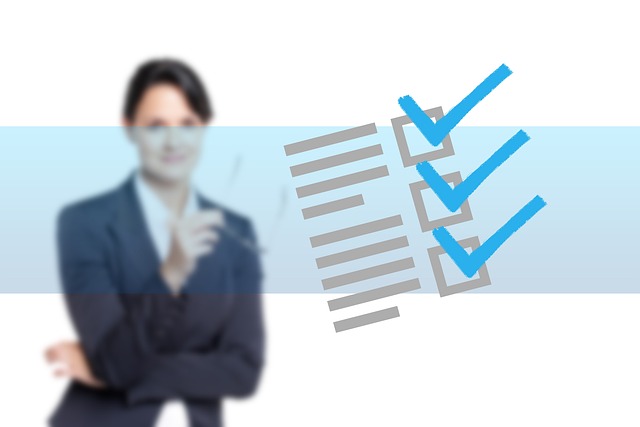
総合商社は就活市場でも非常に人気が高く、内定を勝ち取るには早めかつ丁寧な準備が欠かせません。ここでは、志望者が実践すべき行動を5つの観点からわかりやすく紹介します。
効率的に対策を進めるための参考にしてください。
- 業界・企業研究を徹底する
- OB・OG訪問で情報を収集する
- 語学力・資格を取得してスキルを強化する
- インターンシップに参加して実績を作る
- 筆記試験・テストセンター対策を行う
① 業界・企業研究を徹底する
総合商社の内定を目指すためには、まず業界そのものと各企業について深く理解しておくことが必要不可欠です。
というのも、総合商社はエネルギー、金属、化学品、食料、インフラ、金融など多様な事業を手がけており、各社によって注力分野やグローバル展開の仕方が大きく異なるためです。
たとえば、三井物産は資源分野に強みを持ち、住友商事は社会インフラ事業に積極的です。一方、伊藤忠商事は非資源分野の利益構成が高く、消費関連に強い特徴があります。
こうした違いを把握していないと、どの商社でも通じるような漠然とした志望動機になってしまい、選考官に響きにくくなるでしょう。
また、決算資料や統合報告書を読んで各社のビジネスモデルや中期経営計画を確認しておくと、志望企業がどの分野に投資しているのか、今後の成長戦略はどうなっているのかを把握できます。
自分の関心や経験と企業の方向性が合致していることを示せれば、説得力ある志望理由として評価されやすくなります。
② OB・OG訪問で情報を収集する
OB・OG訪問は、企業理解を深めるだけでなく、選考対策としても非常に有効なアプローチです。
実際に働いている社員から話を聞くことで、パンフレットやホームページには載っていないリアルな情報を得ることができます。
仕事内容の具体例や、入社後に感じたギャップ、仕事のやりがいなど、生の声に触れることで志望動機やキャリアのイメージが一層鮮明になるはずです。
とくに総合商社は、営業職であっても案件ごとの裁量や働き方に大きな違いがあるため、自分が目指したい方向性を明確にするには、複数の社員から多角的に話を聞いておくのが有効です。
業務内容や働く環境、部署ごとの雰囲気など、ネットには出てこない情報にこそ大きな価値があります。さらに、訪問時の態度や質問の内容によっては、推薦やリファラルを得るチャンスにもなり得ます。
そうしたご縁がきっかけでインターンや本選考につながることもあるため、ひとつひとつの訪問を大切にしてください。
訪問後には必ずお礼の連絡をし、得た学びを記録しておくと、面接でも活用しやすくなります。
③ 語学力・資格を取得してスキルを強化する
総合商社の仕事は海外との取引が多く、英語力やビジネススキルが備わっているかどうかが選考において重要な評価ポイントとなります。
TOEICスコアでの判断が主流で、800点以上を求める企業が多く、実際に海外赴任や現地法人とのやりとりでスムーズに英語を使いこなせるかどうかが期待されています。
加えて、簿記や貿易実務検定、TOEFLなどの資格を取得しておくと、経済知識や国際業務への関心の高さをアピールできます。
これらの資格は、単に履歴書を埋めるためのものではなく、「商社で働くために必要な知識や素養を自分なりに補ってきた」という積極性の証明にもなります。
重要なのは、スコアや資格を取得することそのものよりも、それを通じてどのような力を身につけ、将来どう活かすつもりなのかを語れるかどうかです。
たとえば「交渉時に信頼される英語表現を意識して学んだ」「財務諸表が読めるようになり、企業分析に役立てている」といった具体的な学びがあると、評価は大きく変わるでしょう。
スキルは手段であり、それをどのように業務に結びつけられるかを見せることが重要です。
④ インターンシップに参加して実績を作る
インターンシップに参加することは、総合商社の業務や企業文化を理解する最良の手段のひとつです。
グループワークやビジネスケースの検討を通じて、現場に近い課題に取り組む経験は、机上の知識では得られない学びをもたらしてくれます。
実際、参加学生の中から本選考に優先的に案内されるケースも多いため、非常に重要なステップといえるでしょう。
また、総合商社のインターンは数日間にわたるプログラムが主流で、チームでのディスカッションや発表を通じて、自分のリーダーシップやコミュニケーション能力を実感できる場でもあります。
ここで評価された学生には、早期選考の案内が届くこともあり、本選考に向けたアドバンテージを得る機会になります。
参加にあたっては、単に「経験として参加する」のではなく、自分が何を得たいか、どう貢献できるかといった視点を明確にして臨むことが大切です。
終了後は、振り返りをしっかり行い、得られた学びや気づきを言語化しておくと、ESや面接での説得力がぐっと高まります。
⑤ 筆記試験・テストセンター対策を行う
総合商社の選考は倍率が高く、筆記試験で足切りされてしまうケースも少なくありません。
SPIやTG-WEBなどの試験は、問題の量や難易度が高めに設定されているため、事前の対策が成否を分けるといっても過言ではないでしょう。
特にSPIでは、数的処理や論理的読解のスピードが問われ、慣れていないと時間内に終わらせるのが難しい場合もあります。
そのため、早いうちから参考書や問題集を活用し、繰り返し演習を積むことが効果的です。時間を計りながら問題に取り組み、試験のリズムに慣れておくと、本番で焦らずに対応できます。
加えて、企業によってはケーススタディ形式の筆記課題が出題されることもあり、論理的思考力やビジネス感覚を問われる場面もあります。
こうした試験に備えるには、過去に出題された内容や受験者の体験談を参考にして、問題傾向を把握しておくことが有効です。
筆記試験を軽視せず、着実に突破できる実力をつけておくことが、志望企業の面接へと進むための大前提です。
学業との両立は大変かもしれませんが、計画的に取り組んでおくことで、後から焦ることなく自信を持って選考に臨めます。
総合商社で働く魅力とやりがい

総合商社は多様な事業を手がけ、世界を舞台に大規模なビジネスを展開する企業群です。そのスケールやダイナミズムから、多くの就活生にとって憧れの就職先となっています。
ここでは、総合商社で働くことの魅力とやりがいについて、具体的な側面からご紹介します。
- 規模の大きな仕事に関わることができる
- 海外で活躍することができる
- 専門性の高い商材を扱うことができる
- 高水準の報酬を得て成長することができる
① 規模の大きな仕事に関わることができる
総合商社の最大の特徴のひとつが、圧倒的なスケールのビジネスに関われる点です。
たとえば、エネルギー開発や資源輸入など、国家単位のインフラプロジェクトを動かす場に若いうちから携われることも少なくありません。
このような案件では、関係各国の企業・政府・金融機関と調整しながら、数年単位で進行する大型の取り組みが一般的です。
そこでは、情報収集力や交渉力、スケジュール管理など、多様なビジネススキルが実践的に養われていきます。
自分が関与したプロジェクトが無事に完了し、形となって残ることは、何にも代えがたい達成感をもたらすでしょう。
小さな成功体験を積み重ねながら、やがては大規模案件の中核を担う存在へと成長していくことも十分に可能です。
結果として、日々の仕事を通じて社会への影響力や責任の大きさを実感し、それが働くモチベーションへと自然につながっていきます。
② 海外で活躍することができる
総合商社は、海外市場をターゲットとしたビジネス展開を数多く行っており、海外駐在や長期出張は日常的な業務の一部といえます。
英語をはじめとする語学力はもちろん、現地の文化や価値観を理解しながら信頼関係を築くことが求められます。
現場では、日本とは異なるスピード感や交渉スタイルに直面することもありますが、それこそが国際的な感覚を身につける絶好のチャンスです。
現地パートナーや官公庁との連携を進める中で、調整力や判断力も着実に磨かれていくでしょう。
また、生活面でも異文化との出会いが多く、視野を広げるきっかけとなります。言語だけでなく、生活習慣や働き方の違いを理解し適応していく力は、他業界では得にくい貴重な財産です。
将来的には、海外での豊富な経験がキャリアに厚みを持たせ、国内外で通用する人材として大きな武器になるはずです。
③ 専門性の高い商材を扱うことができる
総合商社では、エネルギー、金属、機械、化学品、食料など多岐にわたる分野の商材を取り扱っており、それぞれに高度な知識や専門性が求められます。
とくに、国際的な需給バランスや市場動向、技術革新など、日々変動する情報を正しく把握する力が必要です。
配属される部署やプロジェクトによっては、環境問題や地政学リスク、規制の変化といったマクロな視点でビジネスを捉える力も求められます。
商材に対する理解が深まることで、顧客や取引先からの信頼も厚くなり、より戦略的な関係構築が可能となるでしょう。
さらに、専門知識だけでなく、物流や貿易実務、金融知識など幅広い分野にまたがる理解が必要です。その分、知識の応用力が養われ、他分野への展開もスムーズになります。
このように、商社での経験は単なる営業職にとどまらず、ビジネスプロデューサーとしての視点も自然と身につけることができます。
④ 高水準の報酬を得て成長することができる
総合商社の給与水準は業界内でもトップクラスであり、20代から平均を大きく上回る年収を得ている社員も珍しくありません。
報酬が高い背景には、利益を生み出す力が個人にも求められるため、成果主義の風土が根付いているといえるでしょう。
高い報酬は確かに魅力ですが、それ以上に重要なのが「成果と成長がしっかり評価される環境」であることです。
自ら課題を見つけて取り組む姿勢や、チームとしての貢献度が正当に認められることで、働くうえでの満足感や納得感が高まります。
また、福利厚生や研修制度が手厚く、海外研修や語学支援など、個人のキャリア形成を支える仕組みも充実しています。
こうした環境に身を置くことで、将来の選択肢が広がり、キャリアの可能性も格段に広がっていくはずです。
一方で、プレッシャーや業務負荷も大きくなるため、自分の成長を楽しめるかどうかが長く働く鍵となるでしょう。
総合商社の全体像を理解し、将来像を描こう

総合商社は、トレード・事業投資・事業経営を軸に、グローバルなビジネスを展開する企業体です。
なぜなら、幅広い分野での価値創造と収益の最大化を図りながら、国際的な競争にも柔軟に対応しているからです。
実際に、5大商社は各社異なる強みを持ち、多様な職種と業務内容で世界中に事業を展開しています。そのため、総合商社で働くには企業理解を深めたうえで、語学力や専門スキルの習得が必要です。
こうしたポイントを押さえることで、総合商社の本質や魅力、求められる人材像が明確になり、キャリアの可能性を具体的に描けるでしょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。









