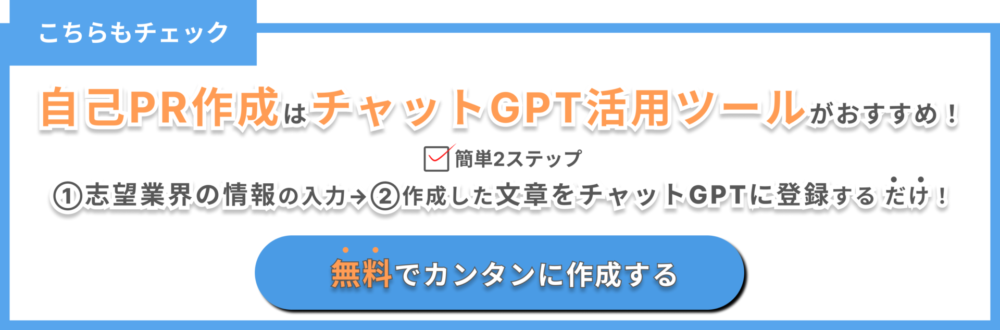面接でフィードバックを受ける時は緊張しますよね。ダメ出しされると落ちたのかと思ってしまいます。
そこで本記事では、就活面接におけるフィードバックと合否の関係や、フィードバックの活かし方を解説します。
フィードバックは成長のチャンスです。この記事を通じて、フィードバックを受けた際の姿勢や対応の仕方を身につけ、内定を勝ち取りましょう。
全て無料!面接対策お助けツール
- 1実際の面接で使われた面接質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作成できる
- 3強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。
面接フィードバックとは面接官からのアドバイスのこと
フィードバックとは、面接官から応募者へのアドバイスのことです。面接に関して応募者の良かった点や改善点を面接官がその場で伝える場合と、後日に電話やメールで伝える場合があります。
面接官からフィードバックを受けることで、自身の改善点や何が良かったのかを知ることができ、それを次の面接に活かすことが可能です。
面接官がフィードバックを行う3つの理由

面接の場で、面接官からフィードバックを受けることは、応募者にとって非常に有益な経験となります。それは、自身の強みや改善すべき点を明確に理解する機会となるからです。
しかし、面接官がフィードバックを行う背後には、企業側の思惑が存在します。ここでは、面接官がフィードバックする3つの理由について詳しく説明します。
- 次の選考も通過して欲しいから
- 企業の印象アップのため
- 指摘への反応を観察するため
明日、面接があるけど不安すぎる…
どんな質問が来るか分からず、緊張してしまう…
このように面接に対しての漠然とした不安から、面接に苦手意識を持ってしまったり、面接が怖いと感じてしまうこともありますよね。企業によっても面接の質問や内容が違うので、毎回ドキドキしてしまいます。
そんな就活生の皆さんのために、カリクル就活攻略メディアでは、実際に400社の面接の質問を調査し、100個の質問を厳選しました。LINE登録をすることで【完全無料】で質問集をダウンロードできます。面接質問集をゲットして、不安を解消した状態で面接に臨みましょう!
\LINE登録1分|400社の質問を厳選/
①次の選考も通過して欲しいから
面接官がフィードバックを行う1つ目の理由は、応募者が次回の選考も通過してほしいからです。
面接官は、応募者が企業で活躍できる人材であると判断した場合、次回の選考も突破できるようにアドバイスを提供します。特に1次面接から最終面接まで、それぞれ採用担当者が異なる場合に顕著です。
現場で実際に働く社員が2次選考以降の面接官を務めるケースが多く、彼らは一緒に働きたいと感じた応募者に対して、次の選考でも好印象を持たれるようなアドバイスを行うことがあります。
②企業の印象アップのため
2つ目の理由は、企業の印象を向上させるためです。面接官は、応募者の能力や人柄を見極めるだけでなく、自社のブランドイメージ向上の役割も担っています。
面接でフィードバックを行う企業はそこまで多くはありませんが、応募者に対して丁寧に改善点をアドバイスしてくれる企業は、良い印象を持たれやすいと言えます。
また、企業は将来有望な人材は取りこぼしたくないと考えるものです。そのため、優秀な人材に対してはしっかりフィードバックを行うことで、応募者の志望度を上げることが期待されます。
③指摘への反応を観察するため
3つ目の理由は、応募者の反応を観察するためです。仕事をする中で、上司から改善点を指摘されたりダメ出しをされる機会は多々あります。
そのため、面接官はフィードバックすることで、応募者が改善点を指摘された際に、真摯にアドバイスを受けとめて、改善しようとする意欲があるのかを見ています。
要するに、フィードバックに対する反応を見ることで、応募者が入社後成長できる人材なのか見極めているのです。
面接フィードバックでダメ出しされても落ちるわけではない

面接フィードバックの内容から直接合否を判断することはできません。フィードバックでダメ出しされたからといって、必ずしも不合格になるわけではないのです。
応募者の成長を望んでいるからこその辛口アドバイスである可能性もあります。企業によりフィードバックのスタイルは異なるため、内容からは合否はわかりません。
ダメ出しを受けたからといってあきらめず、面接官からのアドバイスを素直に受け止め、問題点を改善して次の面接に活かすことが重要です。
また、フィードバックの内容が良かったからといって、油断せず、指摘された改善点を解消し、次回の選考に活かすことが求められます。
面接フィードバックは高評価のサインかも

フィードバックの有無で合否の判断はできませんが、企業は特に有望だとみなした応募者は特別にフィードバックをする場合が多く見られます。
面接官はフィードバックを行うことで、応募者との信頼関係を構築し、入社意欲を高める目的もあるのです。そのため、フィードバックの有無は手応えの基準にはなるでしょう。
【印象アップ】面接フィードバックを受ける時のポイント3つ

面接のフィードバックは、企業からの貴重なアドバイスです。しかし、その受け取り方一つで評価が変わることも。ここでは、面接フィードバックを上手に活用し、内定獲得に繋げるためのポイントを3つ紹介します。
- まず真摯な姿勢で聞く
- メモを取る
- 自分からアドバイスを深堀りする
①まず真摯な姿勢で聞く
まずはどんな意見でも真摯に受け止めることが大切です。
辛辣なダメ出しだと、納得できなかったり、ショックを受けるかもしれません。しかし、その感情をすぐに表に出すと、フィードバックをくれた面接官に対して良い印象を持たれません。
まずは面接官の話を最後まで聞き、課題としてしっかり受け止めることが大切です。
②メモを取る
また、フィードバックは、今後の選考に役立てるための重要な情報です。そのため、積極的にメモを取ることをおすすめします。
メモを取ることで、面接官の話をしっかりと聞いている印象を与えられます。また、フィードバックの内容を後から見返すことで、自身の改善点を再確認し、次の選考に活かせるでしょう。
③自分からアドバイスを深堀りする
フィードバックを受ける際には、自分からもアドバイスを求めることが重要です。
一通り面接官からのアドバイスが終わった後も、自分が気になっていること、聞きたいことを質問して、向上心や主体性をアピールしましょう。
これにより、あなたの意欲や熱意が面接官に伝わります。自ら課題を見つけて改善しようとする姿勢は、仕事でも大切なスキルであり、良い印象を与えられるでしょう。
また、具体的な質問を用意しておくことで、面接官も具体的なアドバイスをしやすくなります。
面接フィードバックを次に活かす2つの方法

フィードバックは、自己改善のための貴重な情報源です。ここでは、フィードバックを最大限に活用するための2つの方法を紹介します。
- 指摘されたところは徹底的に改善
- 褒められたところをさらに強化
①指摘されたところは徹底的に改善
面接で指摘された点は、自己改善のための重要なヒントです。自分では気づかない弱点が見つかるでしょう。指摘された点を改善することで、次回の面接ではより良い結果が期待できます。
具体的な改善方法としては、指摘された内容を深く理解し、それに対する対策を練ることが重要です。さらに、自分1人で考えるだけでなく、模擬面接で第三者に見てもらうと良いでしょう。
また、模擬面接をするなら適切なアドバイスをもらいたい、と考える人もいますよね。そんなときは、カリクルのキャリアアドバイザーに相談するのがおすすめ!
カリクルでは面談を多めに、平均7~8回ほど行っており、その中で模擬面接ももちろん行っています。毎回就活のプロから丁寧に面接のポイントが聞けるので、面接に自信がない人でも問題ありませんよ。
\ 気になる人はこちらから! /
②褒められたところをさらに強化
面接で褒められた点は、自分の強みと言えます。強みをさらに強化することで、自己アピールの力をつけましょう。
褒められた点を強化するためには、その要素がどのように評価されたのかを理解し、それをさらに伸ばすための行動を考えることが重要です。
また、自分の強みを効果的にアピールするために、自己分析を重ねて、強みを裏付ける具体的なエピソードを用意しましょう。
逆質問でフィードバックのお願いはしないのが無難

面接の最後には、逆質問の時間が設けられることが多いですが、その際に、面接官にフィードバックを求めること際は注意が必要です。
なぜなら、逆質問でフィードバックを求める行為は、積極性を評価してくれる面接官もいれば、他社の選考で活かすため、自社を練習台にしているのではとマイナス印象を抱く面接官もいるからです。
ここでは、逆質問でフィードバックを求める際の注意点を2つ紹介します。
- どうしてもの場合はタイミング重視
- 質問は具体的に
どうしてもの場合はタイミング重視
「御社の役員面接に活かしたいため、フィードバックが欲しい」など、入社意欲が高いことが伝わる質問ができるなら、逆質問でフィードバックを求めても構いません。
しかし、逆質問の時間は限られています。そのため、時間が差し迫っている場合や、集団面接の場合は、フィードバックを求めるよりも、自分がこの企業で働く上で何を期待しているのか、どのように貢献できるのかを伝えることが重要です。
こちらからフィードバックを求める際は、その場の空気を読んで、タイミングに気をつけましょう。
質問は具体的に
フィードバックを求める場合でも、質問は具体的にしましょう。あいまいな質問では、具体的な改善点を得ることが難しいと言えます。
具体的な質問をすることで、より有意義なフィードバックを得られるでしょう。
例えば「面接での態度はどうでしたか?」では曖昧すぎます。「話すのが早いといわれるのですが、今日は大丈夫でしたでしょうか?」であれば、具体的なフィードバックばもらえるでしょう。
面接フィードバックを活かして内定に繋げよう
企業によって面接のフィードバックのスタイルは異なります。そのため、フィードバックの有無や内容から面接の合否を判断することはできません。
しかし、面接官からのフィードバックは貴重な情報であり、素直に受け止めて改善・強化すれば、次回以降の選考に活かせることは確かです。
フィードバックを積極的に活用して、志望企業からの内定を勝ち取りましょう。

このメディアの監修者
若林
青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。